
この記事では、点数に関係ない【模試の向き合い方と活かし方】がわかります。
「模試に落ち込んでしまう人」や「模試を最大化したい人」におすすめ!
苦手意識や不安が強くなると、実力が発揮できず、悪循環に陥りやすい。
模試はあくまで練習。
模試は、前日まで・当日・翌日以降で3段活用できる。
点数に関係なく活用するべき。
はじめに:勉強を頑張っているのに、模試の成績が思うように伸びない
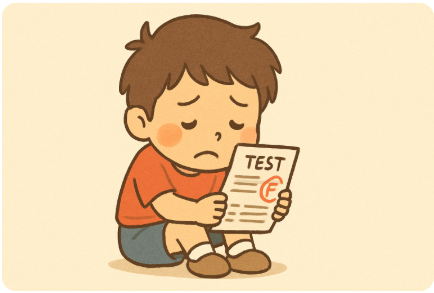
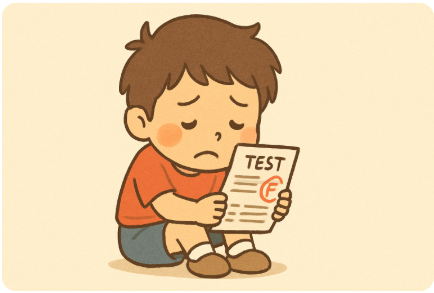



これだけやってもダメなのか・・・
本来は「自分の実力を確認する機会」の模試が、
「不安をあおる存在」になることはありませんか。
模試が近づくと気が重くなる…
テストそのものが苦手になっていく…
そんな状態になってしまう人も、決して少なくありません。
模試の苦手意識が強くなると、どうなるか


模試へ過度に苦手意識が生まれてしまうと、実力が発揮できなくなります。
例えば…
- 問題を解く前から「どうせできない」と思い込み、思考が止まりやすくなる
- 不安や緊張が高まることで、ケアレスミスや時間配分の乱れが起きる
そして、模試で本来の力が出せないと、



国試に受かる気がしない



また失敗するかもしれない
といった不安や諦めに支配され、勉強への集中力も落ちてしまいます。
苦手意識から、演習も形だけになってしまい、手応えを感じづらくなることも…。
結果として、
不安 → 集中できない → 成績が下がる → さらに不安→
どんどん悪循環に陥る危険があります。
模試を無駄にしている典型例です。
そもそも模試の目的はなに?
模試の先にある目的は「国試合格」です。
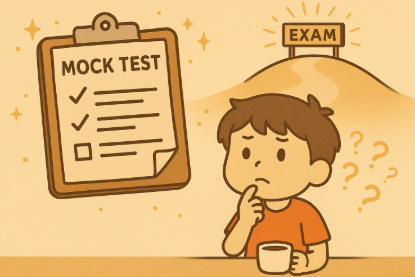
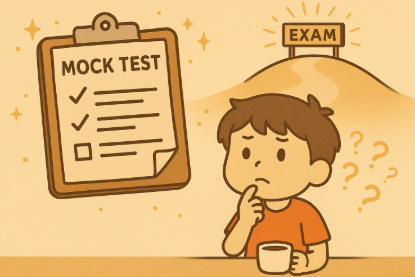
薬ゼミの模試には、どんな特徴がある?
- 薬ゼミが国試を徹底分析して作成する模試
- 12,000人以上が受験する大規模な模試で、全国平均との比較ができる
- 強化すべきポイントが一目でわかる
- 国試当日と同じ時間割で実施される
という特徴があります。
その特徴から得られることは?
- 薬ゼミが考えているやまかけ問題を知れる
- 自分の現在地を把握でき計画の修正ができる
- 自分が時間をかけるべき分野がわかる
- 本番の練習ができる
ということが得られます。
それらを得るのはなんのため?
「国試本番で1問でも多く正答できるようになるため」です。
模試は目的のためのツール
模試での位置は、自分の状況を把握するものにすぎません。
私が、下位2%から1か月で合格ラインまであがったように、
どの位置からでも、追い抜かされる可能性も、追い抜いていく可能性も十分あります。
そんなことを頭の片隅に置いて、
模試と正しく付き合って、頼もしい味方として、合格へ導いてもらいましょう。
模試との向き合い方2選
感情にゆさぶられて、活用を間違えないようにしたいところ。
向き合い方①あくまで模擬試験という視点を忘れない
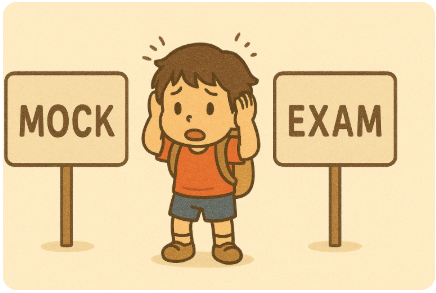
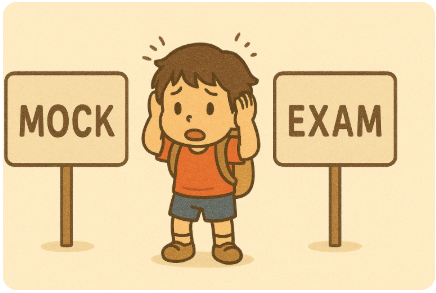
「本番ではない」という視点をもちましょう。
大切なのはその後どう動くかです。
どんな模試の結果であれ、合格の可能性がゼロになることはありません。
うまくいかなくてもいいのです。
だって本番じゃないんですから。
向き合い方②模試のツンデレに付き合う
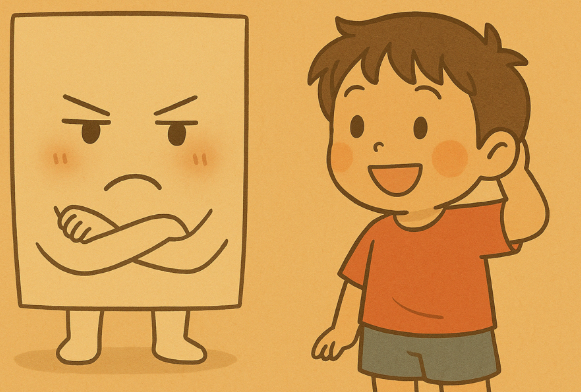
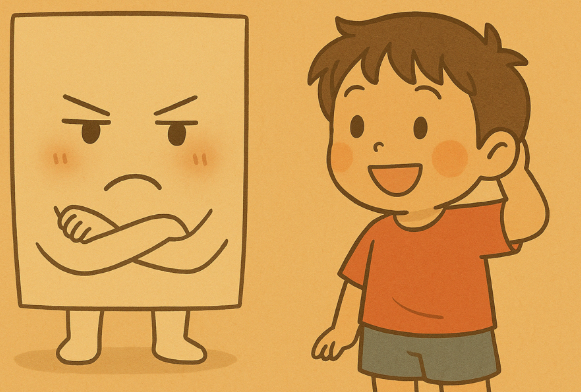
模試は、あなたの努力を否定していません。
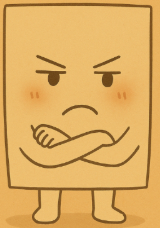
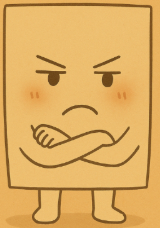
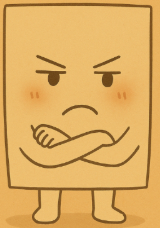
ここがあなたの苦手分野なんだから、がんばんなさい!
と教えてくれています。
どうしても落ち込んでしまう場合は、「間違い」に対しての考え方を変えてみましょう。
間違えたから「気づける」
正解していたら、自分の“穴”に気が付けなかった可能性があります。
点が取れなかった = 今復習すれば、本番でむしろ得点できる
本番で抜けていたら…と考えると、模試で間違えて良かったくらいです。
間違えたから「覚えられる」
感情が強く動いた体験は海馬に強く記憶されます。
つまり、間違えて悔しかった問題の方が記憶に定着しやすい可能性さえあるのです。
「なぜ間違えたのか」「正解は何だったのか」情報処理をすることで、正しい知識を記憶に残すこともできます。
復習すればさらに知識が定着します。
知識量に関係ない模試の活用の仕方
模試の三段階活用に知識量は関係ありません。
模試前の活用


例えば全国統一模試であれば、9月11月1月にあるので、中間目標にしやすいです。
〇点とれるように○○をすると決めることで、だれずに勉強をすすめられます。
模試当日の活用 2選


知識試しの確認はもちろん、知識量に関わらず確認できることも多いです。
模試当日の活用① 本番のシミュレーションをする
前日・当日の過ごし方を意識して、シミュレーションをすることも、模試の活用方法です。
前日の準備、試験中の時間配分、休み時間の過ごし方、ご飯、水分摂取量とトイレ、おやつのタイミング…検証できることはかなり多いです。
模試当日の活用② 解答が全くわからなくても“意味のある時間”にする3つ
- 1.出題意図を探る
正答が全くわからなくても、「どんな知識があれば解けたのか、どの分野のどこなのか、なぜ問われているのか」検討できます。
出題意図を探るだけでも、記憶に残って、復習のとっかかりにも繋がります。
- 2.勉強した範囲か、未知か確認する
「勉強したのに忘れていた」のか、「まだやってない」のかを分けるだけでも、進捗確認になります。
成績に反映されなくても、勉強した部分は着々と解けるようになっていると判明するかもしれません。
勉強した範囲だけで得点割合を出してみるのも1つの手段です。
- 3.間違っていると思った選択肢は訂正までする
もし、うまく訂正できなかったとしても、
復習のときに、自分の考えが全然違っていた!というだけで、感情が動き、記憶につながります。
解答を確認することは必須です。
どんなに知識がなくても、模試を全力で取り組めたら、
確実に模試を受ける前の自分より成長できているはず!
模試後の活用 3選


模試後の活用①解きなおし
解きなおしをどうするかは、
- どんな勉強方法をしているか
- 受験生全体でどんな位置にいるか
- 残り時間とリソースはどのくらいか
などで人によって異なるところです。
解けるまで3回以上やる人、必須だけやる人、正答率60%以上の問題もやる人、全く手を付けない人もいます。
惜しかった問題は、解説を見ないで、使っている参考書で知識を確認しながら、解答を導いている と言う友人もいました。
みっちりやるべき派も、時間はかけるな派もいて、
解きなおしの方法は人それぞれです。
誰かの真似ではなく、「どういう理由でその方法を選んだか」説明できるやり方を選びましょう。
模試後の活用②成績を確認し、計画に反映
- 正答率60%以上の問題を間違えたかどうか(網掛けになっている)
- 平均点と差がある科目はどれか(チャートで確認)
- 現在地はどのくらいか
- マークミス(指示された回答数と異なる問題数を選んだ数)はないか
- 過去の自分の成績と比較してどうか
今後の計画をすり合わせるためにも成績を確認しましょう。
模試後の活用③やまかけ問題集として活用
模試は、データ豊富な予備校が「今年はここが出る」と予測した問題を出している側面もあります。
たとえば、薬ゼミの統一模試とやまかけ講座(国試直前講座)で、第110回では103問的中したとの実績も。
薬ゼミ公式 模試と110回国試比較
本番前の“出題予測された問題集”として、思い切り使い倒すのもよしです。
おまけ:難易度を下げた問題に取り組む
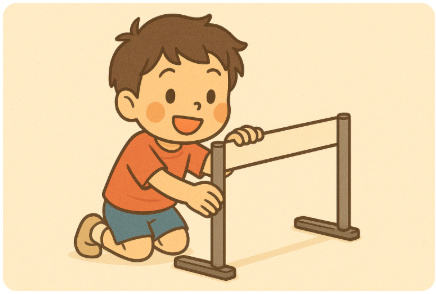
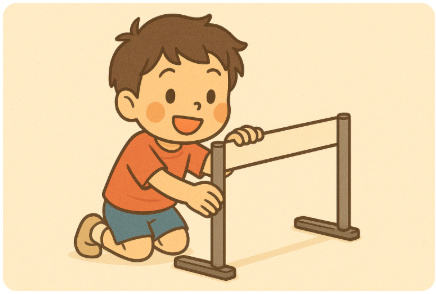
模試が難しすぎて気持ちが折れそうなときは、
必須問題だけに絞って演習するのも1つの戦略。
必須問題は負担が軽く、広い範囲を触れ続けることができる、コスパが高い問題です。
時間が無かった私が使ったのはこれ!





模試はあえて難しくしてるんだもん!!!
と同級生とやんや話したこともありましたが、
それくらいの気持ちで、やる気を立て直す演習に切り替える柔軟さも大切です。
まとめ:模試は敵ではない
どんな成績だとしても、模試は敵ではありません。
ときに、「薬学部に合格し、定期試験も通ってきた自分」を信じることも大切です。
今の自分に足りない部分を知り、
それを一つずつ埋めていける力があると、
信じてあげてください。

