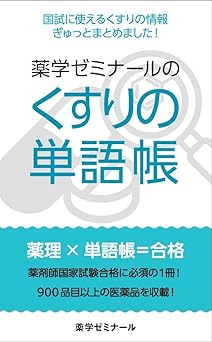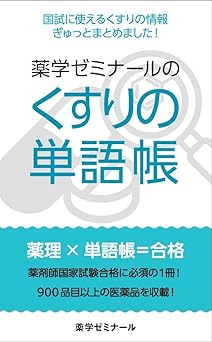この記事では、【勉強量に圧倒されているときの対処法】がわかります。
「青本の1周目すらなかなか終わらない人」や「やってもやっても知識が身につかない人」におすすめ!
全体像が見えないと知識がつながらず、勉強が非効率に。
おすすめ①:要点集で全体を俯瞰し、必須問題で広く浅く触れる学習。
おすすめ②:出題基準をざっと確認、予備校の総評をチェック。
試験範囲が広いときこそ、“全体”から入るのが鍵。
こんにちは!ゴロ助です。
初めて青本を全部手にしたとき、思わず、



え、これ本当に終わるの…?
と固まったことを覚えています。
範囲が広すぎる時のリスク


「木を見て森を見ず」状態になりやすい
1教科でもとんでもなく量が多い青本や領域別問題集。
丁寧に進めても、次から次へと続く未知のページたち。
まるで出口の見えないトンネルを歩いているような、果てのない不安に包まれてしまいます。
細かい部分に気をとられて、全体像をいつまでもとらえられません。
知識がなかなかつながらない
薬剤師国家試験は、単なる暗記ではなく、科目横断的な理解を求められる問題が多い試験です。
そのため、



教科ごとに真面目に勉強しているのに成績が上がらない



学んだ知識がどこか「バラバラ」のままに感じる
そんな感覚に陥り、モチベーションが下がってしまうことも。
ゴロ助の体験談


バラバラの知識がなかなか身につかず不合格
私が不合格だった年を振り返ると、
「今、自分が全体のどこをやっているのか」がまったく見えていませんでした。
出題された問題に対しても、



これはどこの話?



何の知識を問われてる?
という感覚が曖昧で、ただ問題を処理するだけに。



どうすればいいかわからない・・・
そう思いながら本番当日を迎え不合格になりました。
全体像が見えると知識がつながりやすくなる
全体が見えるようになったとき、理解のスピードと深さが一気に変わりました。
例えるなら、幹のない枝を集めてあたふたしていたのが、
幹が見えることで枝をどこに伸ばせばいいか分かり、記憶も自然と整理されていく感じです。
私は合格できた年は、「要点集」を活用して、全体の流れをつかみました。
“要点集を使って合格したゴロ助”が思う「要点集の良いところ・足りないところ」を見てみる
全体をつかむと問題演習も効果的になる
それまで「何を聞かれているかもよく分からなかった問題」に対しても、
問題が“何を問いたいのか”という“意図”のようなものが見え、知識がまとまり、記憶の定着も一気にスムーズに。
要点集はおすすめのおすすめ!!


対策案:実践して効果を感じた学習法
全体像をつかむために効果的な方法を4つご紹介します。
対策① 要点集で“全体の流れ”をつかむ
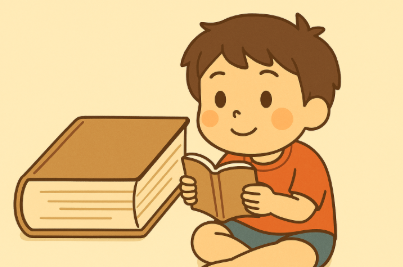
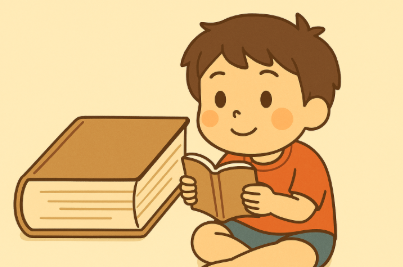
要点集は青本よりよっぽど薄いので全体をつかむのに最適です。
内容を理解して、「全体マップ」を頭に描く感覚で活用します。
学習中も「今、全体のどの位置をやっているのか」を確認しながら進めると、より記憶に定着します。
全教科持ったとしてもそこまで負担ではないため、外出先でもぱっと他の教科も確認しやすいです。
E判定から合格ラインまで到達するために、「全体把握を重視した具体的な勉強方法」をみてみる
対策② 必須問題の演習を繰り返す
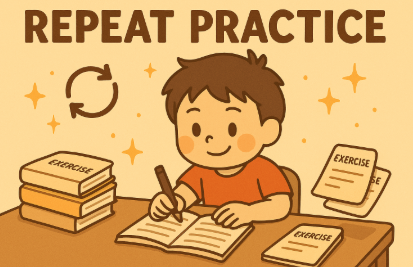
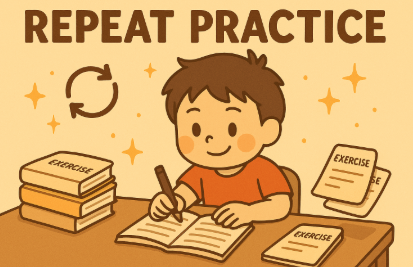
必須問題の演習を繰り返すことも有効です。
必須問題は、
- 理論問題よりも負担が軽い
- 広い範囲に触れ続けられる
コスパが高い学習法です。
教科別に学習していると、前にやった内容を忘れてしまいがちですが、
必須問題だと、全教科に触れ続ける安心感もあります。
私は時間が無くてこれを使っていました


対策③出題基準をざっくり眺めておく
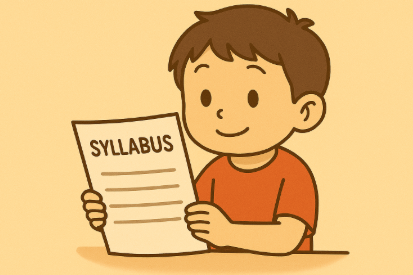
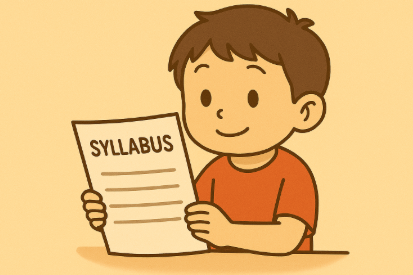
厚生労働省が薬剤師国家試験のページで公開している
「薬剤師国家試験 出題基準(シラバス)」をざっと見てみるのもおすすめです。
「こんな範囲が問われるんだ」と知るだけでも、学習の軸がブレにくくなる気がします。
出題基準に対応しつつ、いつどんな分野が出題されているのかの「出題実績表」がついている予備校教材(青本など)もあります。
それらを見ながら、「今の学習はどこにリンクするか」「よく出る分野か」を時折確認するだけでも、1つの整理になります。
今さら聞けないけど知らないとマズイ「国試の基本情報」を確認しておく
対策④前年度の国試の薬ゼミの総評を確認する


薬ゼミが毎年出している全体総評を確認することで、最新の試験傾向等を確認することができます。
自己採点システムの情報をもとに分析されていて、
- 過去5年の得点分布
- 出題形式別得点率
- 必須/理論/実践問題の難易度や正答率など
- 正答率60%以上の問題
- 合格率・合格者数推移
- 5年間の得点分布
など必要な情報をまとめてくれています。
15分弱の動画なので、移動時間にさっくり見ることができます。
第110回はこちら
【薬学ゼミナール】第110回薬剤師国家試験 全体総評
メディセレなど他の予備校のものもあります!
まとめ:試験範囲が広いときこそ、「全体→細部」の順で攻めよう
試験範囲が膨大だからこそ、“細部”よりもまず“全体”から入ること。
それが、理解・記憶・戦略など、あらゆる面で効果的だったと、個人的には感じています。
迷子になりそうなときは、まず「地図」を広げる。
それが、私にとっては大きな合格へ一歩でした。
薬ゼミは薬の単語帳も出してくれているよ!