
この記事では、【慣れないリスク・国試に向けて慣れるべきこと】がわかります。
「本番までに慣れの準備をしたい人」におすすめ!
こんにちは!ゴロ助です。
また当たり前のことをって思われてしまいそうですが、
「緊急の薬って使って慣れとかないと、いざって時に使えない」って話をしようと思います。
いざ!というときほど、慣れが重要。


私は、急にお腹を壊すことに悩んでいる時期があり、
「いざ!というときのために、カバンに1つ入れておきましょう!」
という下痢止め薬をカバンに常備する毎日でした。
ある日、
私は電車の中でお腹の兆候を感じたものの、停車駅までもう少し先。
これは人様に迷惑をかけてしまう可能性のある重要な局面!
いまがまさに「いざ!」!
さあこの薬を飲む時だ!!!!
・・・・・
・・・・・
・・・・・



え、でもこれ逆に悪化するとかない?!



本当に大丈夫かな?!
普段、いざ!という局面がなかなか訪れないこともあり、その薬の使用経験が少なかった私は、
結局、下痢止めを飲まず、気力で乗り越えることになりました。
国試に向けて、慣れておくべきことって無い?


いつもは夜更かししているけど、今日早く寝れば明日起きれるでしょ!
と思ったけど、1日頭がすっきりしなかった。
この服普段は着ていないけど、今日はこの勝負服にしよう!
と思ったけど、なんだか目立っている気がしてそわついた。
そんなこんなで、ささいなことでも今までと違うことをすると、意外と負担がかかります。
そして、どんな影響が起こるのかわかりません。
国試の場合
国試は、いつもと違う教室・いつもと違う人たち・いつもと違う緊張感…
「いつもと違う」状況が強制的に降りかかってきます。
せめて、自分でコントロールできることは、「いつものルーティーン」までいかなくても、ある程度慣れている状態にしておきたいです。
ポイント
何回かやれば、すぐ慣れるものもあれば、体内時計リセットのように、人によっては2週間~2か月かかるものもあります。
余裕をもって準備しましょう。
何に慣れておくべきなのか、当日までわからないこともありますが、
だからこそ、本番にできる限り近い、会場受験の模試を活かすべしです。
願掛けや、勝負グッズなど、変えるからこそスイッチを入れられるものもあるので、うまく使い分けたいところ。
ささいなことだけど、できそうな対策


大抵のことは、簡単に適応できますが、ちりも積もればなんとやらで、思いつくものを書いておきます。
本番前
- 本番と同じ格好で過ごしてみる
(寒い外、暖かい室内、換気で開けられた窓にも対応できそうか等) - 普段から鉛筆でマークする(鉛筆を使うつもりならば)
- 本番に食べようと思っているものを、本番と同じ時間に食べる
- 普段から腕時計をつけておく
- 本番に飲みたい飲み物を飲んでみる
- 自分が調べた対策は事前にやっておく
(例 おなかが鳴る対策を見つけたから、模試の会場でその動きしてみる) - マスクをしっかりつけて勉強してみる
- いやなことがあっても切り替えられるように準備しておく
- 休み時間をどう過ごすか決めてやってみておく
- 会場を下見しておく
- 1コマ分鼻水をかまないでいられるか/静かに鼻水を処理できるか確かめておく
当日
- ご飯は慣れた地元のコンビニで買ってから会場に向かう
- 慣れていないからこそ早めに出発する
- 勉強は見慣れた資料を使う
- いつも飲んでいる薬を持っていく
脱線小話:腸って第2の脳と言われている
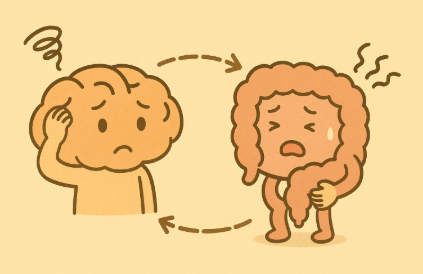
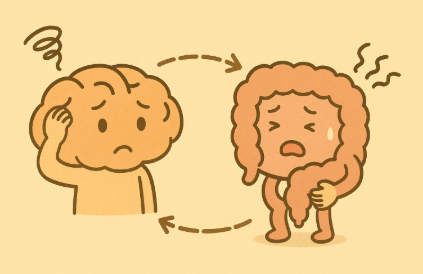
お腹を壊すに関連しての小話ですが、腸脳相関って知っていますか?
腸脳相関とは、腸と脳が密に双方向に影響しあっている関係のことです。
ストレスを感じるとお腹がゴロゴロしだすのは良く知られていますが、実は、腸も脳に大きく影響を与えると考えられています。
腸は第2の脳
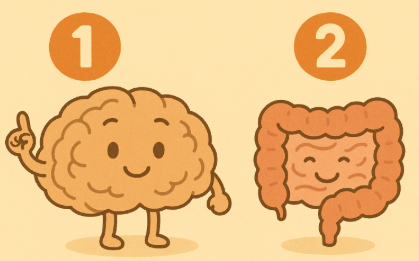
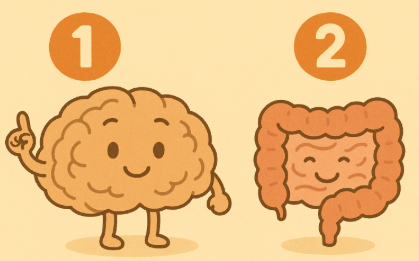
腸は脳に次いで、なんと1億個以上の神経細胞があります。
腸は脳とは独立して自律的に動いており、脳からの信号に頼らず、吸収や排せつなど行うことができるのです。
また、体内のセロトニンの多くは腸で作られています。
血液脳関門を通過できないため、脳に直接移行することはできませんが、腸で吸収されたトリプトファンが腸から脳に送られます。
性格が変わる?


メンタルと腸の関係に着目している人もいます。
マウスの実験ですが、無菌状態のマウスは、通常のマウスと比較してストレスに過敏だったり、正常な社会性を示さなかったそうです。
また、うつ様行動を示すマウスの腸内細菌叢を、うつ様行動を示していないマウスに移植すると、うつ様行動を示すとか…!
腸内細菌をあなどってはいけないかもしれません。
身体は腸に守られている
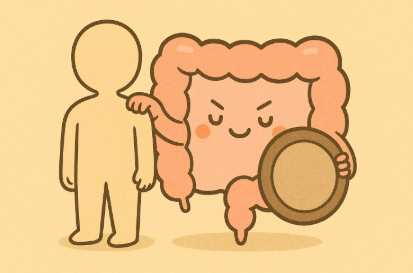
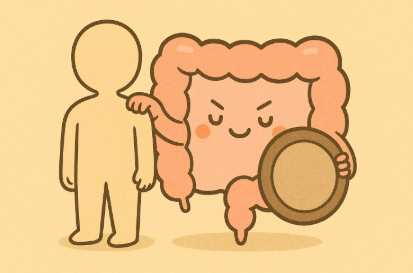
腸には、体内の6割以上の免疫細胞があるそうです。外部からの細菌やウイルスなどから身体を守ってくれています。
そんな腸を守るためにも、生活習慣を正したり、食べるものには気を使っていきたいですね。
結局、何が言いたいかっていうと…
今までしてなかったことを、急に行うと摩擦が発生します。
私は結局、迷走神経反射からお腹を壊すらしく、冷や汗だくだくで意識遠のくレベルのため、試験前の生活から気を付けました。
本当にわずかなことですが、食事・むやみに走らない・腹巻はずっとしておく…などなど、
そんな小さな積み重ねのかいがあったのか、当日は問題なく過ごせました。
みなさんも、自分に必要な「慣れ」を準備しておくとよいかもしれません。

