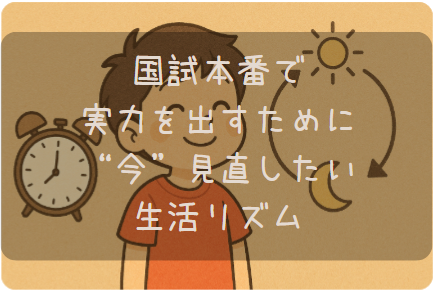この記事では、【夜型のリスクと本番のためにするべき準備】がわかります。
「変えたいのに夜型から朝型に変えられない人」や「本番の朝がどんな感じか知りたい人」におすすめ!
本番は早朝から行動が必要で、夜型だと集中力や思考力が発揮しづらくなる。
寒さや眠気に備えて、体内時計の調整と服装準備も重要。
朝型にシフトするためには、起床時間の前倒し・朝日・食事・スマホ制限などが有効。
はじめに:ついつい夜型になっていませんか?
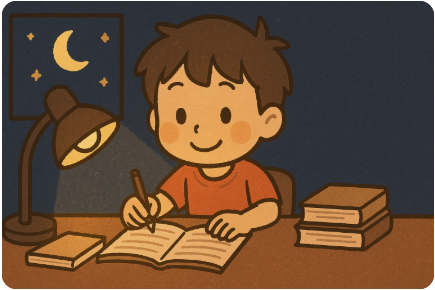
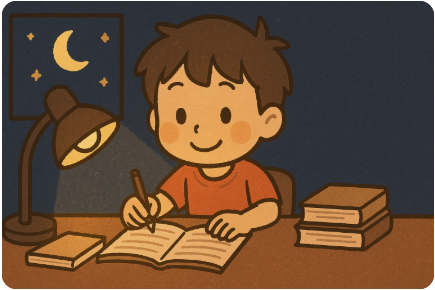
国試が近づくと、焦りから、



あと1問だけ…もう少しだけ…
と夜遅くまで勉強を続けてしまうことがあります。
こうして、“夜に集中する勉強リズム”ができあがってしまう人は少なくありません。
模試なら夜型でも乗り切れるかもしれません。
でも、本番は違います。
本番当日、夜型が引き起こす“落とし穴”


試験当日は電車の遅延や混雑を考慮して、
多くの人がいつもより1時間以上早く行動を始めます。
つまり夜型生活を続けていると、
「いつもより早く起きて、すぐ頭をフル回転させる」という無理を“急に”本番当日にやることになります。
しかも2月の朝は冷え込みが厳しく、雪が降ることも。
早めに会場に着いたはいいものの、開場前に寒い外で待たされる可能性もあります。
眠気 × 寒暖差により、
せっかくの本番で集中力が上がらない──
そんな事態も起こり得るのです。
ゴロ助の不合格経験談
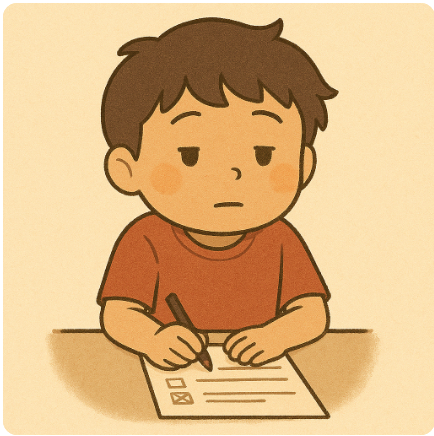
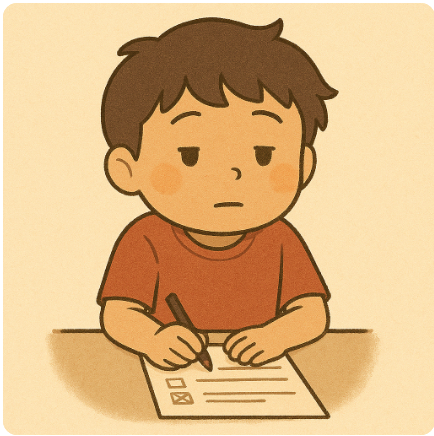
私はもともと朝が苦手で、夜遅くまで勉強し、
朝はギリギリに起きる生活をしていました。
そのため、学生時代は、国試当日も早起きが負担になり、教室に着いても頭がはっきりしませんでした。
すごく緊張しているはずなのに、試験直前のあの独特な空気の中で、



ちょっと眠いかも・・・
と思っていた自分がいました。
対策案:今から“朝型モード”に切り替えよう
眠気と寒さには、体内時計と服装で対策していきましょう。
対策①本番に合わせた「生活リズム」に調整する


試験当日は何時に起きて、何時から集中が必要なのかを意識しながら、
起床・就寝時間を少しずつ前倒ししていきましょう。
体内時計を整えるコツ
- 朝起きたら太陽の光を浴びる
- 朝食をしっかりとる
- 寝る前のスマホやカフェインを控える
- 決まった時間に布団から出る、布団に入る
体内時計のズレは夜ではなく、朝にリセット!
就寝時間にかかわらず、朝、朝日を浴びると体内時計がリセットされて、15時間後くらいに眠くなります。
とはいえ、この理論だと、
6時に朝日を浴びると、21時に眠くなってしまうのですが、
24時までは問題なく頑張れて、その後スッと眠ることができました。
テストの時間に頭が働くように心がけると万全の状態で試験を迎えられます。
対策②朝の寒さに慣れておく


2月の朝は本当に寒いです。
会場までの移動中・待機中の冷え込みに備えて、こんな準備をしておきましょう。
- 外でも中でも快適に過ごせる服装(脱ぎ着しやすい重ね着)
- 会場入りまで待つ時間のためのカイロ・手袋
- 足元から冷えない靴下・靴選び(靴はリラックスできるもの)
体の冷えも、侮ってはいけません。
家で勉強している人は外に出て気温を確かめる日も作ってもいいかも!
私は当日このレッグウォーマーを履いていきました!


まとめ:「万全な状態で挑む」が勝つ
生活リズムを整えると、健康にもつながります。
私は2週間前からは「夜にやりたいことがあっても、朝起きられるように寝る」ことを徹底しました。
具体的には夜12時に寝て、朝6時に起きるという生活です。
午前中に脳のパフォーマンスが高いのは科学的にも証明されています。
「眠くても頑張る」ではなく、
「しっかり寝て、朝からベストを出す」
試験当日に“いつもの力”を出すための準備をすること。
これが、結果的に一番効率のよい勉強法だったと、今では実感しています。