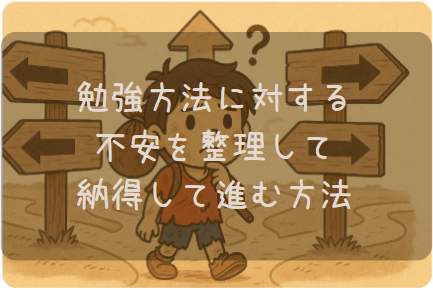この記事では、【勉強方法を探し続けてしまうリスク・理由・対策】がわかります。
「勉強方法がブレ続けている人」や「一つに決めても他の勉強方法が気になってしまう人」におすすめ!
勉強方法を探し続けることは、知識の定着を妨げる。
解決策①:分析麻痺、機会費用について自覚する。
解決策②:プロ(予備校講師など)に客観的な意見をもらう。
解決策③:勉強法を選んだ根拠を言語化する。
不安を整理し、自分軸を持って進むことが成績向上の鍵。
はじめに:勉強法を探し続ける“落とし穴”


こんにちは!ゴロ助です。
薬剤師国家試験の勉強をしていると、



今のやり方、本当に正解なんだろうか…
という不安で、誰もが一度は立ち止まると思います。
特に成績が伸び悩んでいる時期ほど勉強方法の悩みに陥りやすいものです。
「自分のやり方が間違っているのかも」と疑う気持ちが、別の方法への興味を生み、
結果として「勉強方法さすらい人」状態に。
勉強方法を探し続けるリスクってなに?
もちろん、自分に合っていない勉強法を続けるのは非効率ですし、成績も伸びづらいです。
でもそれ以上に、あれこれ迷っている状態が長期間続くと、
- 復習のタイミングがつかめず、反復ができなくなる
- いつまでも1つの教材を最後までやり切れず、全体構造が見えない
- 調べることばかりに時間を奪われてしまう
つまり、“知識が定着しない”まま時間が過ぎていくという状況に陥ってしまいます。
ゴロ助の不合格経験談


私はまさに勉強方法さすらい人でした。
回数別がいい?
領域別がいい?
付箋勉強法?
過去問何周?章末問題?
毎日のように、方法を探し、迷って、悩んで。
気づけば「勉強法を調べる時間」がどんどん増えていきました。
今振り返ると…



“薬剤師国家試験 勉強法”と検索していた時間で、
薬の名前をひとつでも多く覚えたほうがよかった…
と思います。
一つの方法に賭けるのが怖くて、あれもこれもと手を出して、教材だけが増えていく。
「やってる感」に逃げていたのかもしれません。
迷いから抜け出すための3つの対策


なかなか解決しづらい悩みですが、どのように対応すればいいのでしょうか。
対策案①自分の状況を客観視する
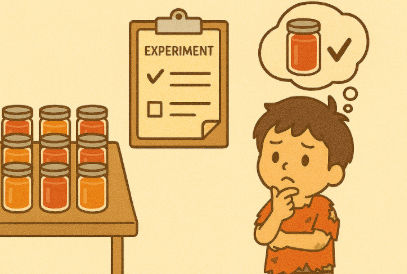
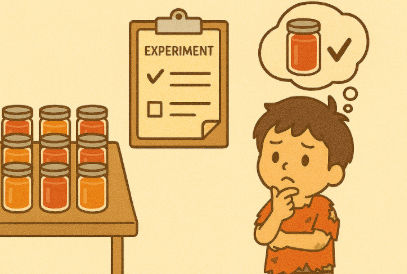
どうして迷ってしまうのか、自覚することがはじめの一歩です。
分析麻痺と機会費用が関係している可能性があります。
分析麻痺
分析麻痺とは、多くの選択肢を比較検討しようとすると、脳が処理しきれずに決断を先延ばしにしてしまうことです。
ジャムの実験を知っていますか?
24種類のジャムを展示した売り場と、6種類のジャムを展示した売り場を比較すると、
購入者が10倍多いのは、6種類のジャムの売り場。
この現象の背景には、選択肢が多すぎることで生じた「分析麻痺」があります。
国試の勉強方法も選択肢が多すぎて、分析麻痺がおきやすいです。
機会費用
諦めた選択肢で得られた利益を機会費用といいます。
多くの選択肢から1つを選んだとき、私たちは、選ばなかった他の選択肢について考えがちに!
選択をするだけで、選択しなかった他の可能性への後悔や疑念が生まれてしまうのです。
国試の勉強方法も、合格のために「完璧な選択をしなければ」というプレッシャーがあるからこそ、
機会費用で他の選択肢から目がそらせなくなり決断を困難にします。
自覚してからが始まり
分析麻痺や機会費用を気にする現象が起きている可能性を自覚し、
どんな選択をとったとしても、完璧なものはなく、一定の基準を満たせばよい
という意識を持つことが大切です。
譲れない基準や期限を設定しておくことも対策となります。
対策案②「人に頼る」という選択肢を持つ


自分ひとりでは解決しづらい時こそ、第三者の視点が有効です。
特に、予備校の先生のようなプロに相談できる環境があるなら、ぜひ活用しましょう。
予備校講師の強み
- 自分では気づけない視点をもらえる
- 自分の状態に合った方法を一緒に整理してくれる
- 長年のデータや傾向から、優先すべきポイントを教えてくれる
という点が強みです。
なにより「プロが一緒に決めてくれた」と自分もより納得して進むことができると思います。
相談の仕方
予備校の授業の機会がある人は、休み時間を利用して、先生に聞いてみましょう。
以下の2つを準備して質問に行けば、きっと実りあるヒントがもらえるはずです。
- 自分が何を聞きたいのか整理すること
- 模試があれば、持っていくこと
もし、授業に参加していない人でも、
予備校に直接問い合わせて面談をお願いすることも可能です。
授業をとっていなかったり、予備校に通っていない人の相談は、業務外の可能性もあるので、事前に電話で相談可能かどうか確認すると安心です。
対策案③根拠をもって、勉強法を選ぶ


自分の中で「これでいく」と納得できるように、
勉強法を選んだ理由を言語化することは、大きな支えになります。
また、言語化の作業で、自然と勉強方法の本質にも着目でき、考えやすいです。
合格した時に行っていた“自己整理の流れ”をご紹介します。
勉強法を選ぶための6ステップ
残された時間、自分の現時点の知識や能力、経験から予測される所要時間、弱点等の把握。
模試の確認、過去問をやってみる、出題要綱を確認するなど。
(例えば…110回までの情報として 既出問題が20%出題されること・65%程度正答すれば良いこと・正答率が60%以上の問題が全体の7割ほどあること は重要な前提条件です。)
今さら聞けない薬剤師国家試験の基本のキ
自分の状況に合わせたメリット・デメリットをあげます。
(例:今の自分には時間が足りないから、この量はできない。この量だと自分には知識が不足してしまう。)
他の手段でデメリットを補完できないか考えます。
(例:覚えるまでに時間がかかりすぎるから、ゴロを活用する。奇数問題だけ解く。)
納得感は迷わずに進むためのカギです。
段階を踏んで「自分で選んだ」と思えると、不安に引っ張られにくくなります。
私の場合は、



今やるべきことは決まっている
と、ぶれずに当日まで走り切ることができました。
結局、このときに間違った方法を選ばないためにも、プロに頼る手段も大切です。
まとめ:不安は消せない。でも、整えることはできる。
- 自分の状況を客観視する
- 分析麻痺が起きていると客観視する
- 機会費用を気にしていると客観視する
- 「人に頼る」という選択肢を持つ
- 根拠をもって、勉強法を選ぶ
勉強法の迷いは、合格への道のりの中で避けて通れない悩みかもしれません。
でも大事なのは、「不安に振り回されないための選び方」を持つことです。
- 選択肢に圧倒されている自分を自覚する
- 一人で抱え込まず、人に頼る
- 「選んだ理由」を言語化する
それだけでも、勉強への集中度は格段に変わります。
あなたの勉強法に「軸」を持たせる一歩になれば幸いです。