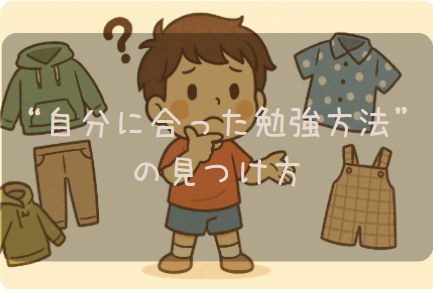この記事では、【合格者の勉強方法を真似するときに気を付けるポイントと対策】がわかります。
「成績が優秀な友達の勉強方法を真似しようとしている人」や「ネットの合格者の勉強方法をそのままやろうとしている人」におすすめ!
合格者の勉強法を真似るだけでは、自分に合うとは限らない。
自分に合う勉強法を選ぶには、現状把握と客観的視点が必要。
勉強法を「こなすこと」が目的になっていないか、定期的に見直すことが重要。
はじめに:大事なことを忘れていませんか?


こんにちは!ゴロ助です。
国試が近づくにつれて、SNSや検索窓に手が伸びるようになりますよね。
私も“自分のやり方で大丈夫なのか”という不安で、
「薬剤師国家試験 勉強方法 9月」「過去問 何周」と、何度も検索した記憶があります。
そんな日々を送る中で、こんな感情が湧いてきました。



このままじゃ受からない。
合格した人の勉強法をやれば、きっと安心できる…
そうしていつの間にか、私は大事な視点を見失っていきました。
大事なことは、
どの勉強法が一番すごいか
どの勉強法が“今の自分”を合格に導けるか
何をやるか・何周するか
自分が合格するために何が必要か
いつ始めたか
自分が合格に間に合うためにどれだけの時間が要るのか
合格者がやっていた
自分が“使いこなせる”か
“当たり前”のことなのに、不安なときほど頭から抜けてしまうのです。
ゴロ助の不合格経験談:真似しただけでは伸びない
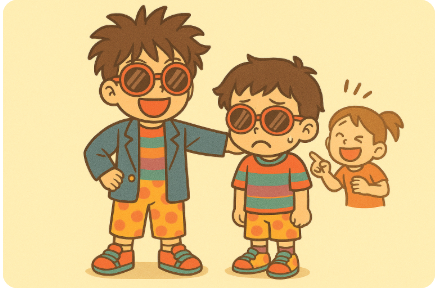
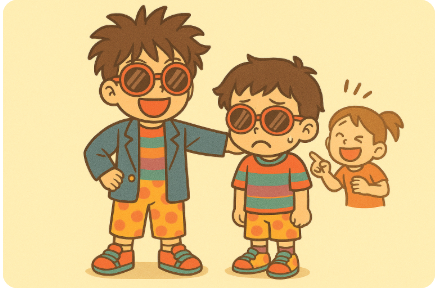
私が学生時代選んだのは、成績上位者の勉強法。
ですが、自分の時間・タイミング・スピードには合っていませんでした。



全然終わらない。
でも、これをやれば成績が伸びるはず…
そんな焦りの中で、「成績上位者の勉強法をやった」と思いたい私は、手順を省略し、「できるところだけ」をやるように。
しかし結果は、やったはずの範囲でさえ点が取れないというもの。
- 合格者のやり方=自分の合格ルートとは限らない。
- 表面的なアレンジは失敗を生む。
そう痛感しました。
対策案:自分に合った方法を見つけるために


国試合格に向けて私たちが目指すべき到達点は、
合格した人の勉強方法を終わらせること
本番当日に合格ライン以上の正答を導き出せるようになること
本当の意味で自分に合った勉強方法を見つけるために、どうすればよいのでしょうか。
対策案①プロに頼る
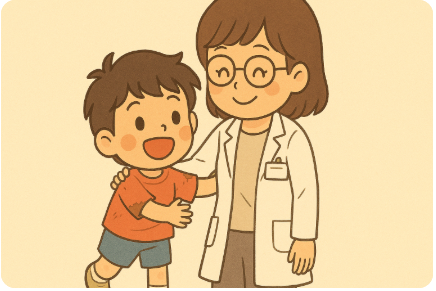
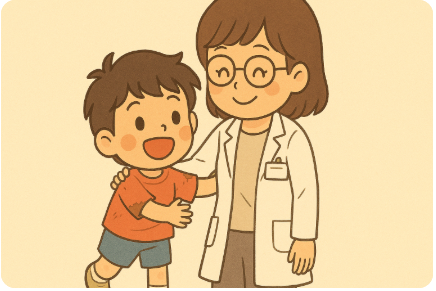
なんといってもプロに相談することです。
やっぱり国試のプロである予備校の先生に頼ることは間違いありません。
予備校は、データと実績があるからこそ、何を優先すべきか、どれをやるべきかわかっています。
成績下位者ほど、人を頼るべきです。
まったく予備校と関わりがない人も、
一度近くの予備校に足を運んでみても良いかも。
今さら聞けないけど知らないとマズイ「国試の基本のキ」を確認する
対策案②自分の現状を正しく把握する
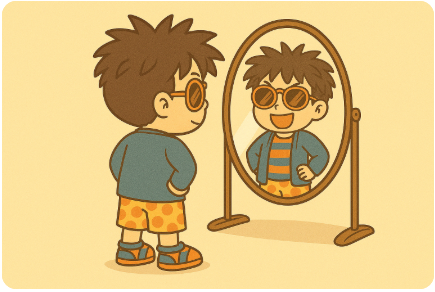
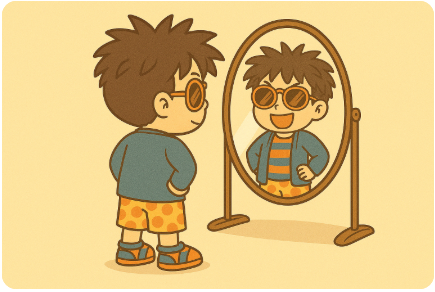
勉強法を判断するには、自分の現状を正しく把握する必要があります。
例えば、以下の6点は明確にすべきです。
- 国試までの残り期間
- 実際に確保できる勉強時間(理想ベースではなく、現実ベースで!)
- 合格に必要な知識(過去問、出題基準や青本の対応表などで確認)
- 自分の位置と到達すべきゴール
- 自分の得意・不得意科目(模試等で確認)
- 知識を定着させるのに必要な所要時間
注意点
- 確保できる勉強時間は、スーパー理想状態の自分で換算しないよう気を付けてください。
予期しないイベントや体調不良などが起きることがあります。
- 実際のところ、作業に必要な所要時間はやってみるまでわかりません。
例えば、1周目にかかる時間、2周目以降に短縮される時間も必要です。
だからこそ、早めの学習開始は有利。
とはいえ、早く始めないと不合格になるわけではありません。
「明日の自分より早く始める」ことができれば、何月からでも遅くはないのです!
対策案③安易なアレンジに注意する


たとえば「過去問を解く」と一言で言っても、
- 問題の出題傾向だけを把握する
- 正答だけ導き出す
- 不正解の選択肢を訂正できるようになる
- 〇△×の印をつけて、〇は2周目以降はどんどん飛ばす
- 周辺知識までがっつり学ぶ
……と、実はその中に多くのやり方が内包されています。
- 細かい勉強方法の内容はどんな方法か
- 勉強法で何を身につけないくてはいけないのか
- 勉強法を省略・アレンジしたとき、本当に実力がつくのか
これらをきちんと見極める意識を持ちましょう。
間違ったアレンジを防止するために「目的と目標の違い」を確認する
まとめ:「勉強法をこなすこと」が目的になっていないか?
「過去問○周」「合格者の方法」──
それ自体は、合格のためのヒントになります。
そして、実際にこなせれば、
これだけの勉強をしたんだ
と、自分の自信を高めてくれる材料に。
でも、自分の合格には何が必要か?という視点を忘れてはいけません。
「勉強法をやり切る」ではなく、
「合格に必要な力を身につける」ために集中する。
“勉強法をこなすこと”が目的になっていないか、
たまに意識してみてください。