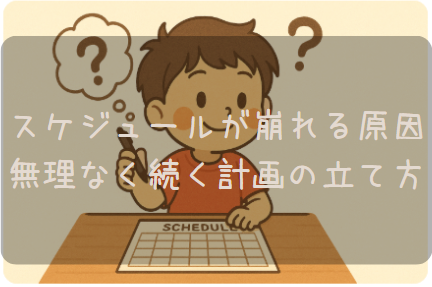この記事では、【効果的な計画の立て方】がわかります。
「計画倒れしてしまう人」や「計画を立てることで満足してしまう人」におすすめ!
「理想の自分」を前提に計画を組むと破綻する。
バッファ日・柔軟性・休息が不可欠。
15・45・90の法則、積み上げ式と逆算式、エビングハウスの忘却曲線の理解が重要。
計画は継続の自信と集中力を支える土台。
こんにちは!ゴロ助です。
国家試験に向けて、



まずは計画を立てましょう
と言う人は多いです。
確かに、限られた期間を最大限に活かすには、計画の設計はとても大切。
だけど、実行可能な計画を立てれていない場合も多いです。
「完璧な自分が前提」の計画を立てていませんか?
安心の理想計画


焦っているときほど、やりがちなのが、“理想だけを詰め込んだ無謀な計画”です。



朝は6時に起きて、朝食も10分で済ませて…



模試の復習も、授業ノートの整理も、1日で一気にやる!



間に合わなければ徹夜でカバー…!
計画を立てているときは不思議と「全部こなせる気」がして、むしろ安心します。
でも実際には、体調不良・急用・眠気・イベント…
思い通りに進まないのが現実です。
理想通りに動ける“完璧な自分”を想定した計画は、まず実行できません。
理想スケジュール中毒者


理想の計画をたててどうなるかというと…
計画通りに進まない → 焦る→
自分を責める → 勉強に手がつかない→
また新しい計画を立て直す →
でもまた実行できない…→
そんな負のループに、はまって「理想スケジュール中毒」になります。
理想スケジュール中毒も含まれる「落ちる学生の特徴」を確認する
効果的なスケジュールが重要な社会人の「落ちる特徴」を確認する
無理なく実行できる計画を組むための4つの工夫
計画は「実行するため」に立てるものです。
予備校の先生が教えてくれた考え方がとても役立ちました。
工夫①
週に1回「何もしない日=バッファ日」を設ける


予期せぬ予定や遅れの調整に使います。
週ごとが難しい場合は、月単位で考えましょう。
工夫②
計画は見直しながら柔軟に調整する


習得状況や所要時間に応じて常に再設計を。
計画を柔軟に見直すためには、長期の計画と、短期の計画が必要です。
勉強計画専門のノートを使うと整理しやすいです。


工夫③
休息も“予定”として入れておく


集中力と定着率を維持するためにも、意識的な休憩は不可欠。
休憩をあえて取り入れる学習
休憩時間を細かく取り入れる学習が効果的とされています。
15・45・90の法則
人が深く集中力を保てる時間は15分といわれます。
この15分が基準となり、一般的な集中時間の45分が授業時間に取り入れられています。
集中力の限界は90分だそうです。
集中力はわずか8.25秒とする人も!
ポモドーロテクニック(25分集中・5分休憩)も使える!
集中力の実験
東京大学 薬学部の池谷裕二教授が、ベネッセと共同で勉強時間と集中力の実験を行っています。
結論としては、
「休憩を細かく取り入れる方が、休憩ごとにガンマ波が回復し、集中状態が維持される」ということです。
実験内容
対象:中学1年生29名
A群→60分連続学習(60分×1セット)
B群→45分連続学習(45分×1セット)
C群→分割学習(15分×3セット=合計45分、各セット間に7.5分の休憩)
内容:中1~中3の英単語を学習
評価:当日・翌日・1週間後に各75問のテストを実施。脳派を計測。
主な結果
学習定着度(1週間後)
15分×3セットグループのスコア伸びが、60分グループより約17%高い(18.75点 vs 16点)
脳の集中状態(ガンマ波)
60分学習では、40分以降にガンマ波が急降下し集中力が低下。
分割学習では、休憩ごとにガンマ波が回復し、集中状態が維持された。
詳細
他の結果はこちら
ニュースを配信する「PR TIMES」のベネッセによる記事
ポモドーロテクニックにピッタリのタイマーを使ってました!


工夫④
人に計画を共有する


一緒に頑張る友人や予備校の先生に計画を共有し、進捗を確認してもらうのも一つの方法です。
アドバイスがもらえるだけでなく、「見られている」という意識が働き、自然と計画を守ろうという気持ちにもなれます。
計画を立てるときに役立つ2つの考え方
次の2つの考え方を計画に取り入れるのも有効です。
考え方①積み上げ式と逆算式


積み上げ式
今の自分ができることから少しずつ積み重ねていく計画の立て方。
柔軟性があり、進捗に応じて内容を変えられる。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 現実に即した計画になりやすい 小さな達成感が積み重なり、継続しやすい | 全体像が見えにくい ゴールに間に合わない可能性がある |
逆算式
最終的なゴールから逆算して、やるべきことを計画に落とし込む方法。
ペース管理や全体把握に有効。ただし、調整力が必要。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ゴールとのズレに早めに気づける 時間管理・優先順位づけに強い | 実行可能性を見誤ると破綻しやすい 予定通りに進まないと焦りやすい |
組み合わせて「大枠は逆算、日々は積み上げ」で運用するのがおすすめです。
考え方②エビングハウスの忘却曲線
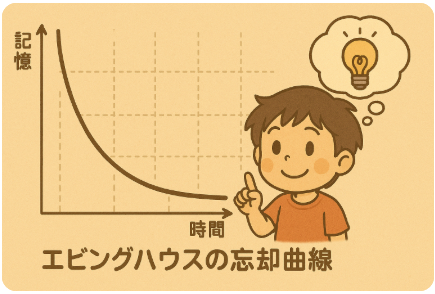
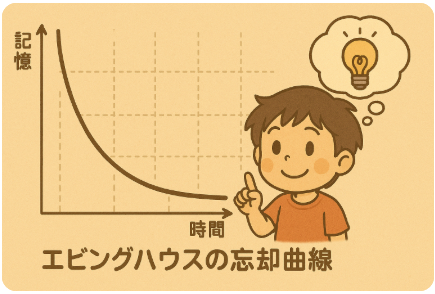
忘却曲線を意識した復習スケジュールもよく耳にしますよね。
エビングハウスの忘却曲線とは…
忘れるまでの時間だけでなく、覚えるまでの時間にも着目して解明されています。
- 人は学んだ内容の多くを1〜2日以内に忘れてしまう。
- 復習をすることで、最初に覚えたときよりも、覚えるためにかかる時間は短くなる。
- 反復のたびに忘却のスピードは遅くなっていく。
そのため、
最初に学んだ日の「翌日・1週間後・1か月後」に復習を組み込むと、記憶が定着しやすくなります。
「無意味な音節」を暗記させた実験結果なので、意味のある知識は、やや記憶が残りやすいとされています。
人によって忘れるスピード・覚えるスピードは異なるため、実際に試しながら調整するのがベストです。
取り入れ方
人によって忘れるスピードは違うので、エビングハウスを目安にしながら、
| 2回目の復習 | 3回目の復習 | 考えられること |
| 全く覚えていない | 全く覚えていない | 周期が長すぎる |
| 覚えている | 全く覚えていない | 2回目の周期が短すぎる/ 3回目の周期が長すぎる |
| ぼんやり覚えている | ぼんやり覚えている | 繰り返す必要がある |
などのように、自分なりに計画をすり合わせてみましょう。
この理論を応用した暗記系学習アプリもあります。(例「Anki」「reminDO」)
伊沢さんの付箋はエビングハウスしやすいです!


まとめ:計画は“自信を積み重ねる道具”
無理のない計画によって、「やり切れる実感」と「達成感」も得られます。
毎日の自信につながり、集中力と安定した気持ちを保つことも。
計画は「合格までの道のりを、安心して進むための地図」です。
まずは実行できる計画を、小さく、柔軟に始めてみてください。