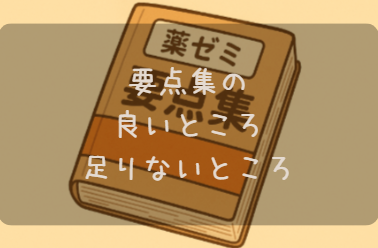この記事では、【要点集の良いところ・足りないところ】がわかります。
「要点集の知識で足りるのか気になっている人」や「要点集を使用するか迷っている人」におすすめ!
こんにちは!ゴロ助です。
私は、全国統一模試Ⅲ 「E判定」(120点以下/345点、下位2%)から主に要点集を使って、109回国試でギリギリ合格に持ち込みました。
1日中勉強できる環境で1か月ちょっと勉強した結果となります。
そんな私が思う要点集の良いところ、足りないところをご紹介します。
走り出す前の準備も重要
準備 編
どんな勉強方法を選ぶかより納得できるかが重要
実際にやった勉強方法の選び方 編
具体的な方法は自分に合ったものを選ぶべし
具体的な勉強方法 編
計画は変更ありき
具体的なスケジュール 編
1か月の勉強以外の蓄積について
忘れてしまった知識は役に立たないのか 編
最後の1か月だからこその揺れへの対処法も重要
最後の1か月のメンタル補強方法 編
同じ成績で違う結果を出したおおまかな違いを紹介
E判定から合格する人と不合格になる人の違い 編
国試当日の具体的な実録
国試当日の実際の記録 編
要点集はこんな本!
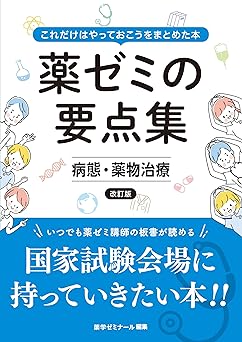
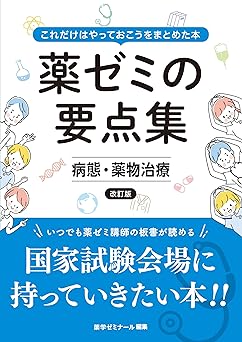
はじめに:要点集はどんな教材か
要点集は、合格ラインに持っていく力がある教材だと思います。
「過去問に目を通す→要点集を覚えて幹をつくる⇔過去問演習・青本」は国試の全体像をつかむ近道になりそうです。
また、もちろん総復習としても、やりやすい教材!
ゴロ助の経験から…
私は、要点集で対策して試験に臨みましたが、
私の状況(国試直前E判定)で、要点集がよかったかは、わかりません!
結果論にすぎないからです。(落ちてたかもしれないし…)
1つ言えるとしたら、もっと時間があったら、要点集を頭にある程度入れた後、絶対に過去問をやっていました。
やっぱり定石は過去問演習です。
要点集はメインではなく、「サポート教材」としてかなりおすすめです。
過去問を一切解いたことない人が、要点集だけをやるとなると、どこを覚えれば良いのかがつかめないかも…
↓要点集を選んだ理由と活用方法はこちらです。
実際にやった勉強方法の選び方 編|統一模試Ⅲ E判定からギリギリ逆転合格②
具体的な勉強方法 編|統一模試Ⅲ E判定からギリギリ逆転合格③
薬ゼミさんの想い(ゴロ助の勝手な推測)
国家試験直前期の総仕上げとして、短時間で必要な範囲に目を通し、勉強の穴がないかを確認するのに適しています。
要点集初版第一刷より
とのことなので、要点集は最後に使って、青本や過去問も使ってねという想いがあると推測されます。
要点集の良いところ
- 薬ゼミが「薬剤師国家試験に向けて絶対におさえておかなければならない」とお墨付きをくれている。
- 薬ゼミ講師の講義の板書やポイントが記載されている。
- しかもその記載が書き文字っぽいフォント。
- フルカラーが眠くなりにくいし、メインのカラーが落ち着いた青色で、集中しやすい気がする。
- 箇条書きや表でまとめてくれているので、そのまま暗記しやすい。
- 覚え方のコツが書いてあって、あえてゴロを探さなくても良い。
- 情報を更新してくれて進化し続けているっぽい。
- 薄いから持ち運びやすい。当日全部持っていってもそんなに重くない。
- 薄いから隙間時間に開きやすい。
- イラストがわかりやすい。
- それなりにメモできる余白がある。
- 個人的にはやまかけと一緒に使えば、薬ゼミの意図みたいのが読める気がする。(大妄想)
- 最短で全体を把握できるので、問題演習も本質的に何を聞きたいのかわかるようになってくる。
- 索引がある。(昔のやつには無かった)
私は要点集で成績が上がったので愛が深いですが、実際に参考書としてよくできていると思います。
正直言うと、学生時代の要点集を使おうと思っていましたが、断然わかりやすくなっていたので、本当に買ってよかったです。
↓全体を把握できないと落ちる要因になります。
要点集だけとなると足りないところ
- 化学と薬剤がこんな薄くていいのか?ってくらい薄い
- 物理、化学、薬剤(計算)、病態はかなり心もとない
- スリム化の影響で、わかりにくい言い回しがある
- スリム化の影響で、理解のための知識が足りないときがある
- 問題演習がついていないので知識の定着や確認ができない(2024年の初版)
- 計算問題対策ができない
- 教科特有の解き方をつかむことができないため、入れた知識を活用できない可能性がある
- 目指す点数によっては、不足
- 出題傾向がわからない
- 本番での既出問題のアレンジ出題の恩恵が得られない
わかりにくい言い回しは自分で理解しやすい形にメモをし直すと頭に入ってきます。
青問や回数別、領域別で問題演習するとバランスがとれそうです。
↓テスト効果は暗記に絶大な力あり
問題演習が勉強に効果的な根拠、知ってる?【過去問演習の効果】
私は時間があまりにも無かったので問題演習は薬ゼミの必須対策問題集でまかないました。
必須の10年間の出題傾向を分析して、出題上位を8割カバーしているので選んでいます。


要点集で足りるか足りないか問題
要点集で足りるか足りないかという点に関してですが、
どこをゴールに置くかで大きく変わると思います。
そして、単純に要点集の知識量の話だけで足りるかどうかを論じているわけでは無いはず…
ゴールがギリギリ合格である場合、完璧を心がければ足りる可能性はあります。
ゴールが余裕をもった合格である場合、いくつかの教科が足りません。
足りないってどういうこと?
多くの人が言っている【要点集は足りない】というのは、
- 知識量が少ない。
- 過去問をやらないと傾向がわからない。
- 計算問題の練習もできない。
- 応用力が養えない。
- 問題演習による知識定着が難しい。
- それぞれの教科特有の解き方もわからないから、知識を活かしきれない。
という【足りない】なのかなと思います。
足りるってどういうこと?
要点集に載っている知識量は、余裕で合格には心もとないものの、充実しています。
薬ゼミが重要と考える知識がまとまっているメリットもある。
実際に要点集で合格していっている人たちは、
- 過去問等で出題傾向をざっくり把握する
- 要点集で勉強する
- 全体の大枠や重要ポイントを最短でつかめる
- 理解が進み、知識が入ってきやすくなる
- 周回しやすいことで知識が強化される
- 知識の土台がある中で、問題演習や青本での補足をして、成績向上が望める
のような感じで、問題演習ありきの要点集主体学習で合格していっているのかなと思います。
なんだかんだ予備校の授業を受けていたり、本当に要点集だけでやってきました!!みたいな人は見たことが無かったです。
ゴロ助の場合
実際に、全国統一模試ⅢでE判定状態の私が、1か月要点集を主体的に用いてどうだったかをさっくりご紹介します。
↓詳しくはこちらから
逆転合格シリーズ
目指していたゴール
60%以上の正答率の問題を確実に取って合格する。
他に使用した教材
- 薬ゼミの必須対策問題集
- 薬ゼミのゴロ集
- 青本の表紙
- やまかけ
- 大学時代の定期試験で使ったノート
結果
ギリギリ合格
本番時点での要点集の習得状況
暗記が苦手な私は、1か月かけても完璧には覚えられなかったです。
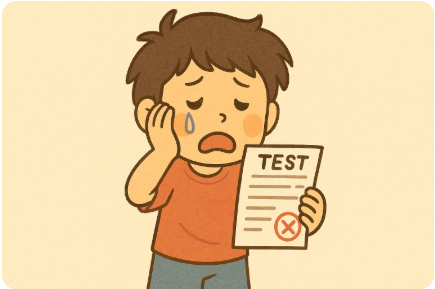
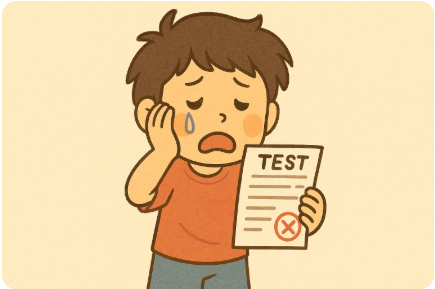
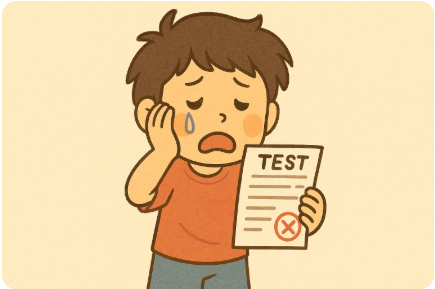
あそこに書いてあったのに…!くっ…!
となる感じでした。
過去問をやった方が良いと思ったのも、知識の定着目的が大きいです。
私の合格にはやまかけ講習の効果もかなりありましたが、要点集と相性は良かったです。
結論
足りるか足りないかは、人によるけれど、良い参考書ではある。
見極めるためにも、自分の状況の理解は重要な気がします…!
要点集がおすすめの人
使い方次第では、だれでも活用できそうですが、
成績が良い人は、総仕上げとして、使いやすい教材!
成績が悪い人は、知識の土台としても使える教材!
かなと思います。
特に、おすすめなのは、
- まとめノートをつくりたい人
- 青本に圧倒されてしまっている人
- 知識が無くて問題がちんぷんかんぷんな人
- 全体像を認識できていない人
- せっかく勉強しているのになかなか成績が上がらない人
- とりあえず最短距離で合格ラインの知識に到達したい人
全体像をつかめると理解のスピードも変わります。
「青本、終わる気がしない…」と感じたら|突破のカギは先に【全体像】を掴むこと。
要点集の手に入れ方
要点集は、amazonか薬ゼミで買えます。
私は、次の日にはもう必要だったことと、薬ゼミに改めて登録をしたくなかったので、amazonでポイントもつけつつ買いました。
おまけ:パレートの法則って知ってる?
80%の結果は20%の要因から生まれるというパレートの法則。
「富の約80%を所有しているのは、人口のたった約20%だった」ことから、ビジネスなどに派生している法則です。
少量の重要な部分が大部分の成果を決めます。
これを勉強にもあてはめると、20%のコアな理解が、80%の効果を生むともいえなくもないかもしれないかもしれない…?
非常に無理やり感がありますが、それくらいギュっとしている参考書でした。
まとめ
私は、もっと時間があったら、過去問演習をしながら要点集に戻ることで要点集を完璧にしながら、成績を上げるという手段をとったと思います。
必要に応じてチョイスしてみてください。