
この記事では、【E判定レベルから合格ラインレベルに成績を上げるために行った勉強方法と詳細なやり方】がわかります。
「どんなことをしたか詳細に知りたい人」や「要点集ややまかけ講習の勉強方法の1例を知りたい人」や「コスパ重視の人」におすすめ!
こんにちは!ゴロ助です。
全国統一模試Ⅲ「E判定」(120点以下/345点、下位2%)から109回国試をギリギリ合格するために実際に行った具体的な勉強方法をご紹介します。
1日中勉強できる環境で1か月ちょっと勉強した結果となります。
走り出す前の準備も重要
準備 編
どんな勉強方法を選ぶかより納得できるかが重要
実際にやった勉強方法の選び方 編
具体的な方法は自分に合ったものを選ぶべし
具体的な勉強方法 編(イマココ!)
計画は変更ありき
具体的なスケジュール 編
1か月の勉強以外の蓄積について
忘れてしまった知識は役に立たないのか 編
最後の1か月だからこその揺れへの対処法も重要
最後の1か月のメンタル補強方法 編
同じ成績で違う結果を出したおおまかな違いを紹介
E判定から合格する人と不合格になる人の違い 編
国試当日の具体的な実録
国試当日の実際の記録 編
正解の勉強方法ではない


これは、「合格できるやり方」ではなく、「E判定レベルの人が、合格ラインに手がかかるところまで上がれる可能性がある方法」です。
この方法だったから、ギリギリだった…ともいえます。
やっぱり定石は問題演習です。
実際に私自身が、国試直後に書いた携帯のメモに、



過去問対策にすればよかったかな…
せめて要点集2周目までしたら過去問に移行した方がよかったかも。
と思っていたことが残っています。
今考えても、知識の定着のためにも領域別/回数別で過去問演習が必要だと思います。
そのため、
こいつ時間足りなかったんだなー
と1つの例として横目で見てもらいたいです!
また、覚え方も人それぞれだと思うので、流し目でお願いします。
使用した教材
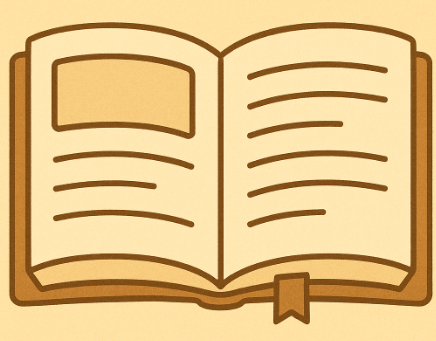
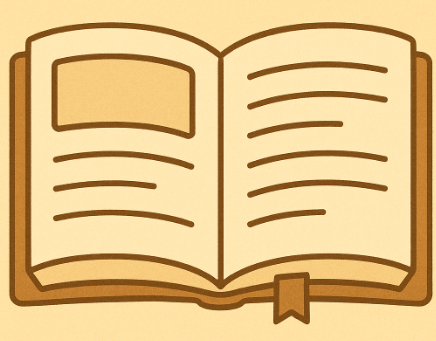
- 薬ゼミの要点集
- 薬ゼミの必須対策問題集
- 薬ゼミのゴロ集
- 青本の表紙
- やまかけ
大学時代の定期試験で使ったノート
実際行った勉強方法


- 出題要綱の確認
- 模試の会場受験
- 要点集(+薬ゼミゴロ)
- 必須対策問題集
- 青本表紙裏
- やまかけ
- 当日の空きコマに確認する資料の作成
勉強方法①出題要綱の確認
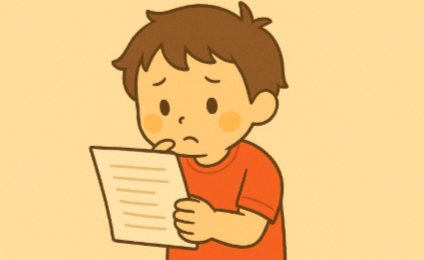
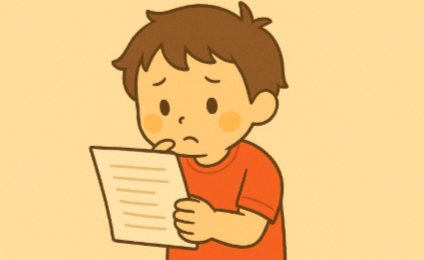
何の教科がどのタイミングで出るのかすら忘れていたので、国試の基本を確認。
この作業は、勉強方法を決める段階でやっています。
勉強方法②模試を会場受験で全集中する


目的
ちんぷんかんぷんだとしても、拘束時間は意味のあるものにする。
方法
模試を全集中で受験。
- 大体どんな問題が、どのコマで出るのか確認
- 時間的な余裕を確認
- 出題意図を探る(軽く余白にメモ)
- どんな知識があれば解けたのか考える(軽く余白にメモ)
- 間違っていると思った選択肢は訂正までする(軽く余白にメモ)
- 本番のシミュレーションをする
- 帰宅後は、解説を確認して自分の考え方を調整する(時間はかけない)
・・・
↓くわしくはこちら
【模試の点数】に落ち込む前に知るべき“向き合い方”|“結果”より“活かし方”が勝負を分ける
勉強方法③要点集を進める


要点集の教科ごとの指針
教科ごとに関しては、できる範囲で指針を確認しながら進める。
↓参考にした指針はこちら
合格者に聞いた教科別の勉強指針
予備校の授業のメモは、要点集であれば、ある程度の板書メモも載っています。
要点集の教科の順番
物理→生物→化学→薬理→病態→衛生→薬剤→法規→実務
平均点が高い薬理は、他より時間もかける。
化学はこんなん足りんだろと思うくらいの薄さだが、難しい問題を解けるようになるためには到底時間が足りないので、必須レベル以上は特別に時間はかけない。(時間が余ったらという意識。)
↓参考にした順番はこちら
現役合格者の勉強方法カタログ(教材は?いつから?何周?)
薬剤は計算対策を計画に組み込むために順番が後ろの方になりました。
要点集1周目(自分が覚えやすい準備をする)
1周目は理解と暗記の準備。ザッと全体を確認してから進む。
要点集にラインを引く
目的
2回目以降の「読む」という時間を節約する。(2回目以降に読む必要のない部分を排除するイメージ)
ラインの引き方
- すでに色がついている部分以外で、2回目以降に確認したいところ(白紙状態から思い出したいキーワード)にラインを引く。
- 常識的な知識や意味のない前振りを排除。
- 2回目以降にラインを追えば、自分がわかる形にすればよいので、教科によっては、単語だけにライン!
【例 様々な病因によってもたらされる慢性の脳疾患であり、大脳ニューロンの過剰な放電から由来する反復性の発作を主徴とする。てんかんの約80%を占め、小児に多い】
- 法規は「〇年」、「〇日」「知事」「大臣」はパッと見ても、すぐ目につくように別の色で丸で囲む。
- 赤シートで消えるペンだとぐちゃぐちゃになる恐れがあったため、マイルドライナーを活用。
線を引く勉強方法は、効果がないとも言われていますが、線を引きながら読むことで、斜め読みにならないというメリットがありました。
要点集にメモをする
目的
要点集だけを確認すれば良いように集約する。
方法(3つ)
- 作成したゴロや覚え方を書き込む。
- 理解を助けるメモを書き込む。
- 薬ゼミのゴロを一気に確認して、該当部分にメモする。
要点集の理解を意識する
目的
理解して暗記事項を減らす。
方法(2つ)
- どうしてもすんなり頭に入らない部分
どうしても頭に入らないところは、何回も見たときにわかりやすい形に整理。
ルーズリーフだと、無意識に丁寧にやらなきゃ…となってしまうので、amazonのペラペラの紙と青ペンを使う。 - どうしてもわからない部分
全くわからないところは、いったんネット等で調べる。
青本だとあれも見なきゃと目について、制限が無くなってしまうので、まずネットでピンポイントに確認。
それでも不明であれば青本確認。
自分が読めればOK!
要点集を覚えようとする
目的
白紙の状態やキーワードだけの状態から、知識を思い出せるようにとっかかりを作る。
方法(3つ)
- ゴロを作成する。
薬理に関してはすべての薬のゴロを作成。 - 紙に青ペンで書きなぐる/ノート型ホワイトボードに書きなぐる
書く感覚も記憶の助けになったので、書きなぐる作業も導入。
特に薬理の受容体や薬のメカニズムのイラストは、白紙から書く。
(自分がわかれば良いので、「ヒスタミン受容体」を「HR」と書くなどして省略。)
他の人からは単に手を動かしているだけに見えるレベルの書きなぐり。 - 文章をそのまま覚えるのではなく、自分が思い出せる形で覚える(ファインマンテクニックを意識)
頭の中だけだと、つい「できたつもり」になってしまいがちなのを、書く動作で防いでいました。
【薬理】が全然覚えられない…そんな私が「苦手な薬理」を「得点源」に変えた方法
暗記の工夫の調査報告
ゴロのリスク|安易に使っていない?
要点集2周目(アクティブリコール、ファインマンテクニックを意識)
- 小さい単元を自分で説明しようとしてから、読み直すことで、疑似問題形式に。
- ゴロであれば、キーワードからゴロが出てくるか、ゴロの意味がわかるかを確認。
- 1周目と同様に書きなぐりながら暗記。
ポイント
- もともと色がついている部分は思い出す作業を重点的に。
- こだわりすぎず、知識が出てこなければ、即読み直し。
2周目で、思ったより覚えていない現実に、心が折れそうになりました。
「これでいいのだろうか」が頭をもたげますが、納得して選んだという事実で前に進むことができました。
↓アクティブリコールはこちら
問題演習が勉強に効果的な根拠、知ってる?【過去問演習の効果】
↓ファインマンテクニックはこちら
「とりあえず覚える」は危険!【理解】に時間をかける意味と対策
3周目以降
- 1回目と違うペンで、苦手だなと思うところはラインで強調していく。
- 「思い出そうとする→確認する」の繰り返し。
ポイント
- もし最後の周回まで覚えていなかったショックがあっても止まらない。
- “今”覚えればいいし、試験直前に最高量の知識を持っていればいいから、1つでも多く頭に入れるという意識を保つ。
全体として、こだわりすぎず、時間がかかりすぎる部分は、飛ばしていきました。
だんだん全容がぼんやりと頭に入って、なにがどこに書いてあるとか、ゴロを思い出せるとかいう状態になりました。
他の教科をやっているときも、ここなんだっけ…と教科をまたいで確認していました。
方法④必須対策問題集を進める


問題演習としては、必須対策問題集を活用。
10年間の出題傾向を徹底分析し、出題上位を8割カバーし、予想問題も多数収録している代物!
目的
知識定着の確認。必須対策。テスト効果の活用。
実施タイミング
要点集で1教科が終わったタイミング。
実施回数
要点集1周目+ラストに時間があったらの2回やるのが理想。自信のあるものは解きなおしなし。
全教科は2周できなかったです。
実施ポイント
わからなければ即解説を確認。
解く前は、解けるようになっていなかったらどうしようと現実と向き合うのがすごく怖かったです。
方法⑤青本の表紙の裏を確認する


青本の表紙の裏に、公式等がまとまっていたので、毎日複数の教科に触れられるように活用しました。
使いやすい形に変える
- 表紙がはがれるようになってたので、はがす
- 背表紙の部分は取り除いてA4サイズにする
- 穴あけパンチで左上に穴をあける
- 紐で結ぶ
確認タイミング
隙間時間に確認していました。
- トイレ中
- ご飯を作っているとき
- ご飯食べているとき
- 移動中
- 寝る前
- 朝起きたとき
やり方
- 1周目はなにが書いてあるか確認する。
- 2周目以降は、いったん思い出そうとしてから確認する。ゴロなど工夫をメモする。
要点集が進んでいくと、思い出せるようになっていくので、思い出せなくても気にしませんでした。
方法⑥薬ゼミのやまかけ講習受講する
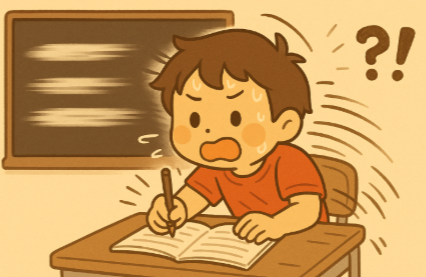
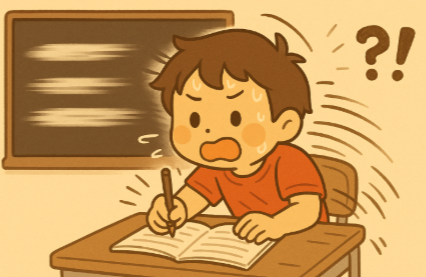
薬ゼミのやまかけの講習は、本番の2日前に実施。
その頃には、やまかけ資料に載っている知識が、要点集にあった/なかった はわかるようになっていました。
要点集にない情報は、「薬ゼミが絶対大事としている要点集に乗っていない情報=新しい知識 or 今回出る可能性が高い」と勝手に認識していました。
活用の仕方(この方法は見た目悪くなるので工夫必須)
やまかけの授業は1教科10分とかなので、すんごい速いです。MAXの集中力で挑まないと置いて行かれます。
オンライン授業は事前に資料を確認できました。
目的
- 自分が復習しなくてはならないところを明らかにすること
- 直前に山掛け資料さえ見ればある程度確認できるようにすること
方法
- 授業の前
自分がしっかり覚えていないところに線を引く。
授業後だと、純粋に覚えていないのかわからなくなってしまうので、事前にやる。
必要であれば要点集に戻る。 - 授業中
先生に“ここに線を引け”と指示されるので引く。(色も複数指示されます。) - 授業後
先生が確認しておけといったところを確認する。
余白が小さいので、付箋や小さな紙にメモをしてやまかけの資料に貼る。
やまかけの資料を見れば完結するようにする。
ゴロも書いておく。 - 前日
自分がまだ不安なところに線をひく - 本番1日目の後
薬ゼミのオンライン授業(無料)があり、1日目に出題された箇所から2日目はここが出そうと分析してくれる。
更に線の引き直しが指示されるので、マーカーの取り扱い注意。
この方法だと、線が重なったところ(「自分が覚えていない」かつ「先生が重要と言った」)が一目瞭然で、優先的に復習できる。
休み時間はそこをマストで確認!
1日目に出題された部分だとしても、自分の知識が不安であれば2日目も確認していました。
全部マーカーでやった結果、威圧的な資料になりました。(モザイク処理しています。)
全部マーカーはお勧めしません!
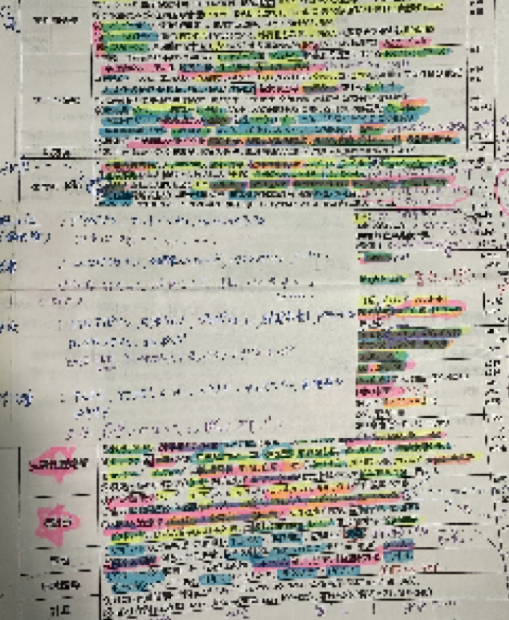
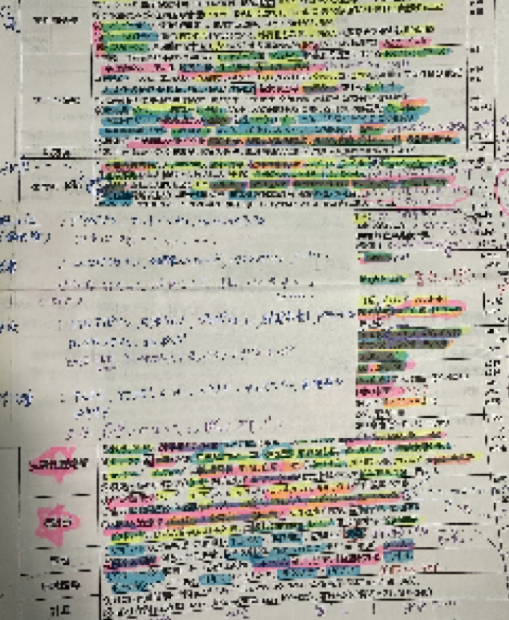
【薬理】が全然覚えられない…そんな私が「苦手な薬理」を「得点源」に変えた方法
方法⑦休み時間の確認資料を作成する


直前に確認する資料は事前準備が必要です。
私は、本番の休み時間に確認するものは、やまかけの資料と青本の表紙にしました。
やまかけの資料と青本の表紙は、スマホで写真を撮っておいて、電車の中やトイレ待ちは、スマホの画像を確認していました。
やまかけの資料は、教科をまたいで出題されると思っていたので、全教科確認していました。
1時間の密度を最大化するために、“今”すべき準備【試験直前・当日の過ごし方の改善】
薬剤師国家試験 【模試】と【本番】の違い|私が驚いた“思わぬギャップ”とその対策
その他


大学の定期テストの時に使ったノートを見返すこともありました。
また、今まで蓄積していた知識は全く無になったわけではないと思います。
まとめ:合格に必要だと確実に言えること
成績を短期間で大きく伸ばした人は、全員言っていることかもしれませんが、
私が確実に言えるのは、どんな方法だったとしても、「諦めないこと」が絶対に必要ということです。
準備期間から本番2日目が終わるまで。
自分に合った方法で、諦めずに走り抜けましょう。

