
この記事では、【やる気が出ない原因と対策のヒント】がわかります。
「なかなかやる気が出なくて困っている人」におすすめ!
やる気が出ないことは、“意志の弱さ”ではなく“脳の仕組み”が原因かも。
自己効力感の向上など心理学的アプローチで再起動できる。
「やる気を出す」のではなく、「やる気の土壌を整える」設計するのが効果的。
可能であれば、なにも考えず今すぐやる。
専門的知見ではありません。
はじめに:やりたくないな…と思ったことはありませんか?


やる気が低下してしまう
国試の対策は「やるしかない」とわかっていても、
「国試のやる気が低下する時期」を多くの人が経験するのではないでしょうか。



またさぼってしまった



意志が弱いから勉強できないんだ
やる気が低下すると、つい自分を責めがちになります。
やる気が低下するのは意志のせい?
やる気の低下が起きるのは、「意志が弱いから」ではありません。
脳がやる気の出ない「状態」になっているに過ぎないのです。
やる気は、ドーパミンやセロトニンなどのホルモン分泌にも強く影響をうけます。
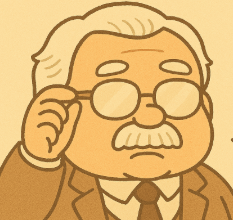
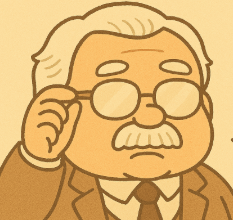
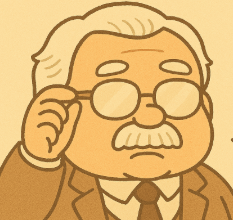
とにかく始める!いますぐ!!
それができないときは、
自分の状態を把握し、ホルモンが出やすい習慣を工夫して、やる気の土壌を整えていきましょう!
なぜやる気は低下してしまうのか?
まずはやる気がでない原因を把握して、自分の状態を客観的に認識します。
原因①心理的な安全を確保をしている


脳は「失敗の予感」を感知してしまうと、自分を守るために動き出します。
- 「やってダメだった」よりも「やらなかった」で自尊心を守る
- やる気に関連するホルモンを分泌しない
- 「できなかった自分」と向き合うという苦痛を避ける
・・・
そして、結果として「なにもしない(回避)」選択がとられ心理的な安全が確保されます。
失敗の予感の要因
脳が失敗を予感する要因としては、
- 課題が大きすぎる/難しすぎる
- 他人と比較して劣等感を感じている
- 完璧主義の性格
などがあります。
国試の場合
勉強量が果てしない国試の勉強も、脳は「失敗の予感」を感知しやすくなります。
その結果、脳が自分を守ろうと、「なにもしない」という選択をとるのです。
原因②“決定疲れ”が起きている


「決定疲れ」とは、多くの選択や意思決定を繰り返し、判断力が低下することです。
つまり、決定を繰り返すほど、脳は疲れていくのです。
ネットショッピングをしているとき、最後にいらないものを買ってしまった経験はありませんか?
「決定疲れ」を起こしていると、衝動的な選択が増えてしまったり、自己否定につながる場合も。
決定疲れの要因
ただ生活するだけでも、小さな決定の積み重ねで脳は疲れています。



今日は何を着ようかな?
それすらも決定の1つです。
国試の場合
受験勉強では、選択の瞬間がさらに訪れます。
- どの科目を勉強するか
- 何時から始めるか
- どの教材を使うか
・・・
そして、決定に追われて「決定疲れ」を起こすと、一時的な快楽や楽な行動に流れやすくなります。
結果的に、SNSやスマホに逃げてしまったり、自分は集中力が無いと思い込んでしまうことも。
原因③内発的動機づけが低下している


「内発的動機づけ」とは、「自分の内側から湧き上がる動機」のことです。
| 内発的動機付け | 外発的動機付け |
| ・報酬や他者の期待関係なし (自分の中に理由がある) ・持続性が長い ・例:興味があるから勉強する | ・報酬や他者の期待から生まれる (外から理由が与えられる) ・効果が一時的 ・例:ほめられるから勉強する |
内側から自然にわくやる気と、報酬や圧力から生まれるやる気がある!
内的動機づけの要因
内発的動機づけは3つの心理的欲求が満たされる必要があります。
- 自律性(自分で選んでやっていると感じること)
- 有能感(自分はできると実感できること)
- 関係性(誰かとつながっていると感じること)
どれか1つでも欠けると内的動機づけは弱まると言われています。
国試の場合
長期に及ぶ国試対策においては、持続性のある内発的な動機づけが、重要な役割を担います。
対策:やる気の土壌を育てる6選
やる気が出ない異常状態を回復するには、
- 脳に失敗を予感させない
- 決定疲れを起こさない
- 内的動機づけを育てる
が、考えられますが、具体的に何をすればよいのでしょうか。
やる気対策①自己効力感を上げる


自己効力感とは、「自分にはできる・うまく対処できるはず」という予測や信念のことです。
自分にはできるという感覚によって、脳は失敗の予感を感じにくくなり、
やる気に関連するホルモン分泌や行動につながります。
やることが多すぎたり、難しすぎたりすると、「自分には無理」と感じて、自己効力感が低下します。
国試における自己効力感の上げ方
- 目標を細かくする
- 行動のハードルを極限まで下げる
- 成果を可視化する
- 片付いた空間で勉強する
などがあります。
やる気対策②判断の負荷を減らす
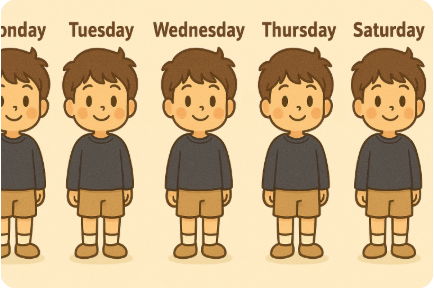
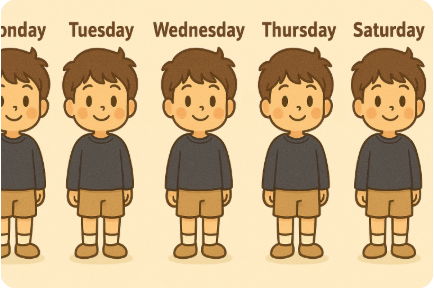
勉強に集中できるよう、必要性が低い判断は減らしてしまいましょう。
判断を減らす①普段の生活を習慣化する
食事や服などを固定すると、生活における判断の回数が減ります。
小さな判断の積み重ねを減らしていきましょう。
私は、食事のメニューと服装の固定によって、勉強以外を考える時間をあまり持たないようにしていました。
できる限り本番に近い習慣にするために、模試と本番の違いを確認しておく
判断を減らす②実行のトリガーを作る
実行のトリガーとは、「いつ・どこで・どのように行動をとるか」あらかじめ決めておくことです。
“場所・時間・行動”を決めておくだけで、実行率はグッと安定します。
例
- 朝起きたら、青本を開く
- 夜ごはんのあと、20分だけ薬理の復習をする
- お風呂の前に、今日の振り返りをする
「過去問をやる」
「月水金の19時に薬理の過去問を30分やる」
判断を減らす③教材は絞る
あれこれ教材を比較しないとならない状況を無くしましょう。
教材を絞ると、復習しやすいメリットもあります。
判断を減らす④時間で区切る
量で終わりを決めると、予想外に時間がかかったときに、続けるのかやめるのか決断に迫られます。
「30分薬理の問題を解く」など制限時間で区切ることで迷いを断ちましょう。
もし、制限時間で自分が想定していた量が終わらないのであれば、計画の見直しが必要です。
問題数で区切る方が良い場合もあるので使い分けてください。
やる気対策③関係性を持つ
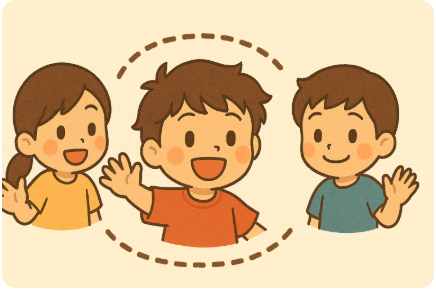
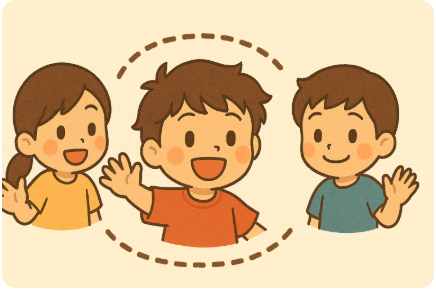
つながりの中でやる気が育ちます。関係性は、内的動機づけ(自分の中に理由があるやる気)に必要です。
例
・進捗をSNSやLINEで誰かに報告する
・応援メッセージや目標を目につく場所に置く
・仲間がいる環境に一度足を運ぶ
好きな予備校の先生に、応援メッセージを書いてもらうのも効果的。
やる気対策④自律性を取り戻す


自律性は自分で選んでやっていると感じることです。自律性は、内的動機づけ(自分の中に理由があるやる気)に必要です。
例
・これさえやれば寝て良いと“自分で”決める
・「やらなきゃいけない」から「やると決めた」に言い換える
・合格した自分にとって良い未来を想定する
小さなことから自律性を取り戻しましょう。
免許が不要だと思う時は自律性がさがりやすい!不合格になる辛さを確認して自分の気持ちを再構築するべし
やる気対策⑤プライミング効果を利用する


プライミング効果とは、直前に受けた刺激が、その後の行動や判断に無意識のうちに影響を与える心理現象です。
例
- 「努力」「達成」「合格」などポジティブ言葉
- 「合格通知」「勉強する自分」のイメージ
- 前向きな音楽
これらが無意識のうちに「やる気スイッチ」として働きます。
ピザって10回言うだけで、ひじをひざと言ってしまうのを考えても、意外と効果は強いです。
私は、好きな曲を聴くことで、ぬるっと勉強を始めていました。
集中しはじめると音楽が邪魔になって、音楽に頼らず勉強することも可能です。
やる気対策⑥身体を整える


基本的なことですが、やる気に関連するホルモンを分泌しやすい身体を整えることも大切です。
例
・朝、日光を浴びる
・軽い運動をする
・十分に睡眠をとる
・食事をしっかりとる
・・・
とはいえ、秒で取り掛かるのが1番だったりする


対策を上げてきましたが、いろいろごちゃごちゃ考えず、とりあえず解き始めるのが1番早かったりもします。
1問がすんなり解けて、そのまま気持ちよくすすむこともあれば、
1問が解けなくて、焦りでそのまま机にむかうこともある。
あーやる気でない…。さ、やろう。
を試みるのも良いかもしれません。
「やる気」なんて概念そもそも存在しないかも…?
まとめ
- 心理的な安全を確保をしている
- “決定疲れ”が起きている
- 内発的動機づけが低下している
- 自己効力感を上げる
- 判断の負荷を減らす
- 関係性を持つ
- 自律性を取り戻す
- プライミング効果を利用する
- 身体を整える
- 秒で取り掛かる
やる気が出ないことは、自分のせいではなく、「状態」に過ぎません。
無理にやる気を出そうとするのではなく、状態を整えることで、当たり前に勉強できるようになります。
自分を責めずに、小さな積み重ねの継続で、行動できる環境を作っていきましょう。
ちょっと重たいけど、やる気ペンってのもある。



