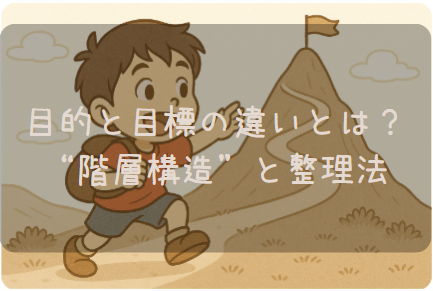この記事では、【目的と目標の違いと注意点・効果的な目標の立て方】がわかります。
「目的と目標の違いがあまりわからない人」や「目標の立て方がいまいちな人」におすすめ!
「目的」は“なぜそれをやるのか”という方向や意義。
「目標」は目的に向かうための具体的な達成点や行動指標。
目標だけに集中すると、本来の目的を見失いやすくなる。
SMART原則を取り入れる。
はじめに:目的と目標をなんとなく使い分けてない?


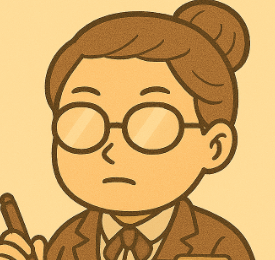
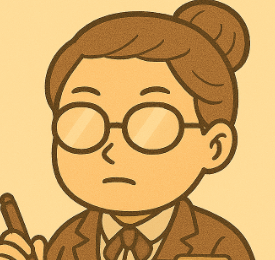
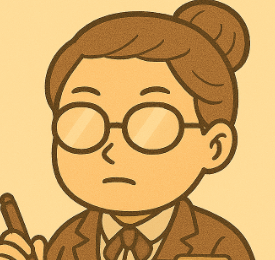
「目標」を立てましょう



「目的」を明確にしましょう
よく言われることではあるのに、
正直、私は「目的」と「目標」をなんとなくで使い分けていました。
就職後、目的と目標を使い分ける場面が多かったですが、
薬剤師国家試験も、この2つをきちんと理解して整理することが大切です。
使い分けがうまくいっていないと、
- 努力の方向性を見失う
- 本質的な学習からはずれてしまう
- 挫折しやすくなる
- メンタルが揺れる
- 優先順位を間違える
- 結果的に遠回りになってしまう
などのリスクが高まります。
ぜひ、目的と目標の使い分け・注意点・効果的な目標の立て方を確認してください!
目的と目標、それぞれの定義
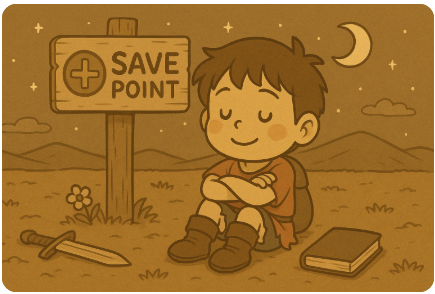
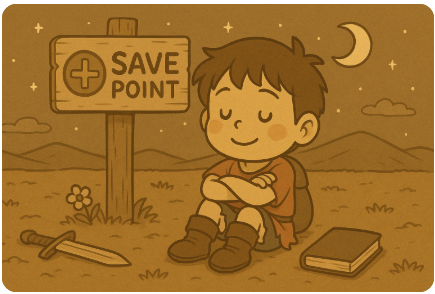
目的:最終的に達成したい方向や意義。「なぜそれをやるのか?」
目標:目的に向かう途中の具体的な達成点や指標。「何を・どこまで・いつまでにやるか?」
たとえるなら、
目的は“コンパス”(進むべき方向)
目標は “チェックポイント”(向かう途中の目印)
目的があるから目標に意味が生まれ、達成可能な目標があるから目的に近づいていけます。
目的と目標を使い分けて考えると、やるべきことが整理され、努力の方向がブレにくくなるのです。
目的が定まっていない場合
目的が定まっていないまま目標を立てても、
途中で「なんのためにやってるんだっけ?」と迷ってしまう。
目的が定まっている場合
明確な目的があると、多少しんどくてもでも目標に向かって努力し続けられる。
「免許が不要だから薬剤師になる明確な目的は持てないよ」というときは不合格で失うものを確認する
目的と目標の「階層構造」と「目的のすり替わり」
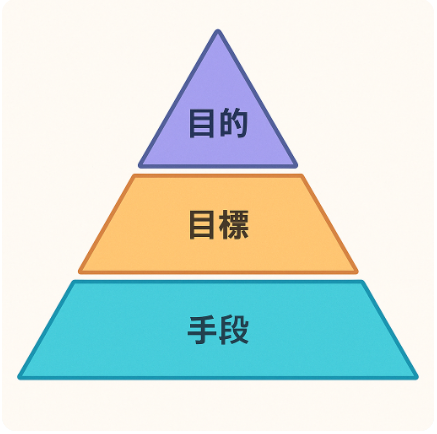
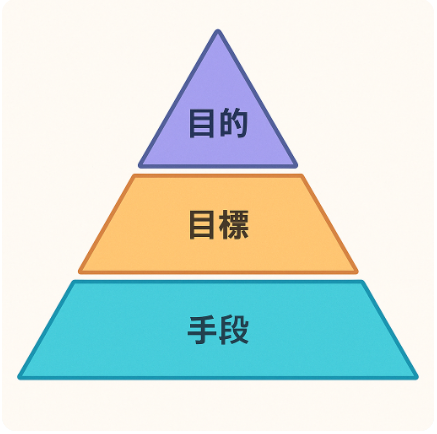
目的を達成するために、中間目標があり、さらに目標を達成する行動目標があります。
大きな目的 → 中間目標 → 行動目標 → 日々のタスク
このように目的・目標・手段は、階層構造になっています。
階層構造になっている目的と目標は、「目的のすり替わり」に注意が必要です。
国試を用いて“すり替わり”についてご説明します。
薬剤師国家試験の場合
【最終目的】
国家試験に合格する
【中間目標(目的のための目標)】
模試で300点取る
【具体的な手段(行動目標)】
過去問を3回解く
「国家試験に合格する」という目的に対して、
「模試で300点取る」という目標を立てたとします。
さらに、
「模試で300点取る」を達成するために、
「過去問を3回解く」という“目標”を立てると…



さっきまで目標だったはずの「模試で300点取る」が、
いつの間にか“目的”になっている?
そんな風に感じませんか?
目的と目標のすり替わり
目標は目的を達成するための“手段”です。
しかし、
①「国家試験合格」を達成するために「模試で300点」を目標にする
だから、
②「模試で300点」を達成するために「過去問3回」を目標にする
というように、上の段階の目標は、次の段階では“目的”のように機能します。
このような“目的のすり替わり”が、起こりやすいのです。
すり替わりが起きると何が起こる?
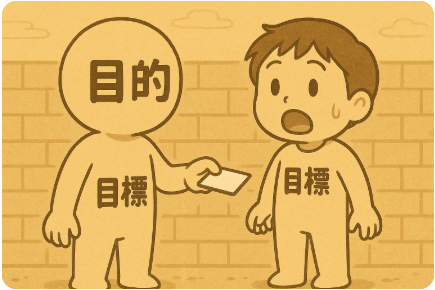
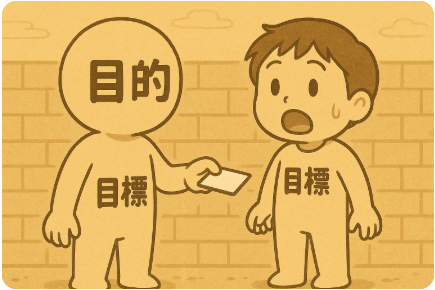
中間目標が最終目標化するとなにが起きるでしょうか?
国試を例にすると…
例①
「国家試験に合格する」が目的なのに、
「模試で300点取る」ことが目的になる。
その結果、点数に一喜一憂したり、数字だけを追い始めてしまう。
例②
模試で300点とるためなのに、
過去問を3回解くことが目的になる。
その結果、作業だけを繰り返す。
このように、目的と目標がすり替わると、学習の本質からずれてしまいます。
今やっていることは何のため?
その目標の“上の階層”にある目的は?
と常に自分に問い直してみてください。
誰かの勉強方法を真似するとき、目的を見失いがちになるのを確認しておく
効果的な目標の立て方


すり替わりを防ぐためにも、SMART原則を意識すると効果的な目標が立てやすくなります。
S「Specific」(具体的)
目標は明確で具体的でなければなりません。
「何を」「誰が」「どこで」「なぜ」「どのように」を明確にすることで、目標に向かう道筋がはっきりします。
目標の具体例
「成績を向上させる」
「過去問の正答率60%以上の問題を確実に解けるようになることで、全国統一模試Ⅱの点数を前回より100点向上させる」
ポイント
- 行動を表す動詞を使用する(増加させる、削減する、完成させるなど)
- 対象を明確にする(何の模試か、どの科目か、どの単元かなど)
- 期待される結果を詳細に記述する
M「Measurable」(測定可能)
目標は、進捗状況や達成度を、数値や指標で測定できなければなりません。
そのために、現在の位置と最終目標までの距離を把握する必要があります。
測定指標の具体例
- 模試の成績、過去問演習での点数
- 完了した問題数、正答率
- 時間(短縮時間、作業時間など)
目標の具体例
- 「点数を向上させる」
「全国統一模試で7割以上を獲得する」 - 「勉強に集中する時間を増やす」
「1時間集中して10分休憩する」
A「Achievable」(達成可能)
目標は、現実的で達成可能なものでなければなりません。
高すぎる目標は挫折をまねき、低すぎる目標はモチベーションを下げます。
達成可能の判断に必要な要素
- 現在の能力
- 利用可能な時間
- 外的要因(遊び、付き合いの飲み会等)
- 過去の成績や経験
ポイント
現在の能力を10-20%上回る程度の目標が、モチベーションとのバランスが良いとされています。
R 「Relevant」(関連性/現実的)
目標は、より大きな目的と関連していなければなりません。
なぜその目標が重要なのか、どのような意味があるのかを明確にする必要があります。
確認の具体例
- 自分の人生の目指す方向とあっている?
- 達成したら、どんな価値が生まれる?
- 現在の優先順位の中で、どの位置?
T 「Time-bound」(期限設定)
目標に明確な期限を設定すると、緊急性や計画性が生まれます。
日々の行動での優先順位をつけやすくなります。
効果的な期限設定例
- 最終期限だけでなく、中間の期限も設定
- 現実的で余裕を持った期限を設定
- 突発的要因まで考慮し、バッファを確保した設定
まとめ:“なぜがんばるのか”を見失わない
目的を達成するために、目標を設定する。
そして、目標に集中しつつも、その先にある本当の目的を忘れない。
進む道に迷ったときこそ、
自分が「何のために」「どこへ向かって」「今何をやっているのか」をクリアにしながら進んでいきましょう。