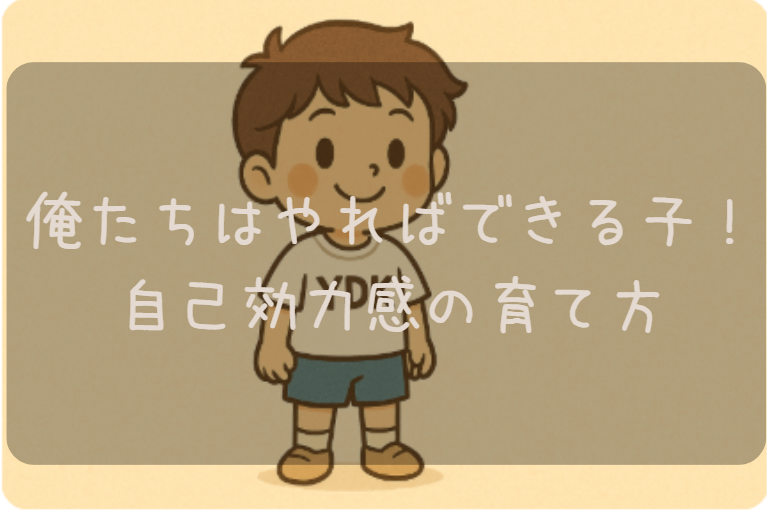この記事では、【自己効力感について・自己効力感の育て方・育てる時の挫折の対処法】がわかります。
「どうせムリだという感覚から抜けられない人」や「できる感覚を高めたい人」におすすめ!
- 自己効力感は達成する能力がある感覚
- 自己効力感が高いと、困難に直面しても諦めずに取り組んで良い成果を上げる。
- 小さな積み重ねで自己効力感は上げられる
無理かもって思っちゃうよね


こんにちは!ゴロ助です。
どうせ自分には無理かも
やっぱり自信がない
そんな気持ちの奥にあるのは、“自己効力感”の低さです。



自己肯定感はなんとなくわかるけど、自己効力感ってなに?
知ってみると、自己効力感こそ国試を戦い抜くために必要な力だと実感します。
自己効力感高く国試に挑むために、
- 自己効力感について
- 自己効力感の要素
- 自己効力感のチェック方法
- 国試での具体的な自己効力感の育て方
- 困難に立ち向かう時の対応
をご紹介します。
自己肯定感と自己効力感
自己肯定感は聞いたことあっても、自己効力感はあまりきかないで
自己効力感ってなに?
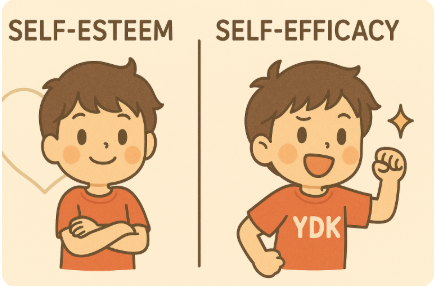
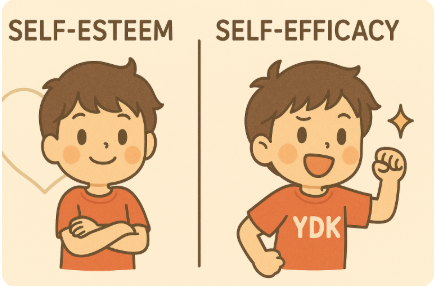
自己効力感とは、「特定の課題や困難に対処できる」という感覚です。
経験や環境で育つ後天的な「力の土台」。
よく耳にする自己肯定感と、似て非なるものです。
| 自己効力感 | 特定の課題や状況に対して「達成する能力がある」という感覚。 具体的なスキルや経験に基づく。 |
| 自己肯定感 | 自分の存在そのものを価値あるものとして受け入れる感覚。 成果や能力に関係ない。 |
自己効力感は、具体的な課題に対しての感覚です。
自己効力感をあげるメリット


自己効力感が高い人は、困難に直面しても諦めずに取り組み、より良い成果を上げる傾向があります。
自己効力感が高いと…
- やればできる感覚があり集中力が持続しやすい
- 難しい問題にも粘り強く取り組める
- 本番で実力を発揮できる
・・・・
自己肯定感と自己効力感はどちらも大切ですが、今回は自己効力感に着目します。
自己効力感が育つ4つの要素
自己効力感が育つ要素は、大きく4つあるとされています。
要素①遂行体験(成功体験)


自己効力感の最も強力な源は、成功体験です。
困難な課題を自力で乗り越えた経験は、「自分にはできる」という確信を深めます。
小さな課題でも、積み重なると大きな自信となります。
重要なのは、成功体験を意識的に認識することです。
成功体験は自己効力感を向上させる最も強力な要素です
要素②代理的体験(他者の観察)


自分と似た状況の人が成功している姿を見ると、



自分にもできるかもしれない
という期待が生まれます。
自分により近い特徴を持っている場合、より期待は強くなります。
要素③言語的説得(周囲からの励まし)


周囲の人からの、
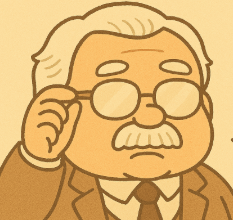
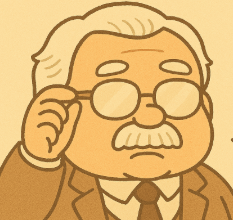
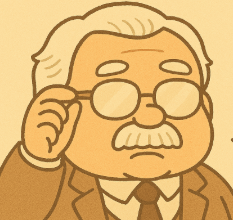
あなたならできる
という言葉も、自己効力感を形成します。
自分自身への言葉も重要で、否定的な言葉を、肯定的で現実的な言葉に変えていく練習が効果的です。
社会人受験の人で、周囲の声が力になる場合は国試受験を宣言しても良いかも
要素④情動的・生理的喚起(気分や体調の影響)


不安や緊張、疲労は、自己効力感に影響します。
リラックスした状態や、適度なストレス状態で課題に取り組むと、高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。
睡眠、運動、瞑想などで心身の状態を整えると、自己効力感の向上につながるのです。
環境の変化で、体調や気分に影響が出ちゃうときの対策もみておく(社会人向け記事)
自己効力感をチェックしてみる?


自己効力感を測るセルフエフィカシー尺度は様々ありますが、よく目にするものはこちらです。
YESかNOでこたえます。
問いに対してYESでもNOでも、どちらが正しいも正しくないもありません。
ー行動の積極性ー
1.何か仕事をするときは、自信を持ってやるほうである。
2.何かを決めるとき、迷わずに決定するほうである。
3.結果の見通しがつかない仕事でも、積極的にとりくんでゆくほうだと思う。
4.どんなことでも積極的に、こなすほうである。
5.ひっこみじあんなほうだと思う。
6.人と比べて心配性なほうである。
7.積極的に活動するのは、苦手なほうである。
ー失敗に対する不安ー
8.過去に犯した失敗や嫌な経験を思いだして、暗い気持ちになることがよくある。
9.仕事を終えた後、失敗したと感じることのほうが多い。
10.何かをするとき、うまくゆかないのではないかと不安になることが多い。
11.どうやったらよいか決心がつかずに仕事にとりかかれないことがよくある。
12.小さな失敗でも人よりずっと気にするほうである。
ー能力の社会的位置づけー
13.友人より優れた能力がある。
14.人より記憶力がよいほうである。
15.友人よりも特に優れた知識を持っている分野がある。
16.世の中に貢献できる力があると思う。
坂野雄二 (1986), 一般性セルフ・エフィカシー尺度作成の試み, 行動療法研究, 12(1), 73-82.
セルフ・エフィカシーの臨床心理学 坂野雄二・前田基成著
1~4・13~16:YESを1点
5~12:NOを1点
としたときに、
8点以下→自己効力感が低い、という一つの目安になるそうです。
自己効力感は後天的なものなので、上げていくことが可能です。
次に国試に着目した、自己効力感の上げ方をご紹介します!
国試に着目した自己効力感の育て方 7選
先ほどの4要素を実際にやっていきます。
- 遂行体験(成功体験)
- 代理的体験(他者の観察)
- 言語的説得(周囲からの励まし)
- 情動的・生理的喚起(気分や体調の影響)
特別なことを成し遂げる必要はありません。
やろうと思ってできたことの蓄積が、自分への信頼を少しずつ取り戻してくれます。
育て方①小さな目標を立てる


大きな目標を小さなステップに分解しましょう。
例:「青本を1周する」→「“用量と作用の単元”をやる」
ポイント
- 完璧主義になりすぎない。
- 目標と目的のすり替わりが起きないように注意する。
80%の達成でも十分価値があります!
育て方②行動のハードルを極限まで下げる
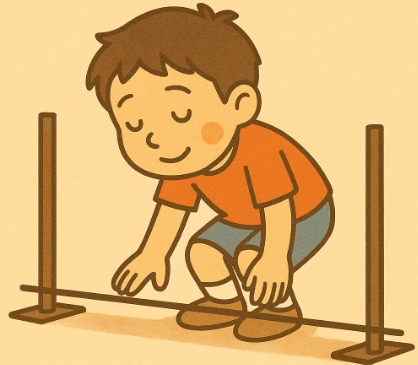
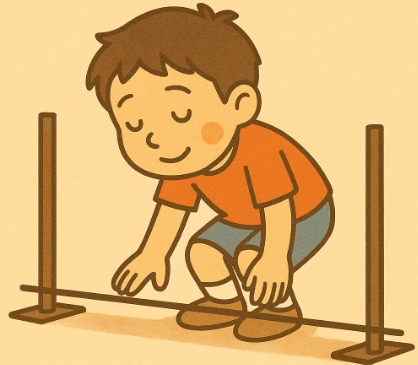
「これだけならやれる」ものをやればクリアにしましょう。
「机に座った」でもOKです。
気分がのればそのまま続ける、のらなければ終わらせます。
結果的に5分のつもりが30分…と集中につながっていく場合も。
例
・タスクの中で、一番小さなものを完了する
・正答率が高い問題だけやる
・問題文を1問だけ読む
ポイント



1問やったら結局100問やらないといけないしなあ
という意識になると結局腰が重くなるので、本当に終わりにしましょう。
そして、行動できた自分をしっかり認めましょう!
育て方③成果を可視化する
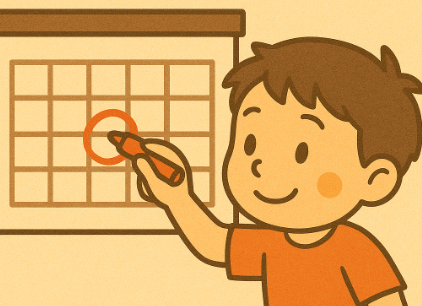
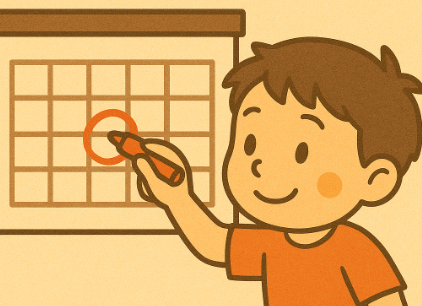
“進捗”を可視化すると、自己効力感が上がります。
例
・携帯アプリで記録する
・スケジュール帳に計画だけでなく、やったことも書いていく
・1秒でも勉強できた日に丸をつける
・できない問題に印をつけるのではなく、できた問題に印をつける。
アプリもあります!(例 DotHabit)
育て方④片づいた空間で勉強する


片づいた机に座ると「自分は準備できている」という感覚が強まり、自己効力感を高める手助けになります。
また、整理された環境では目からの情報量が下がって、脳が無駄に疲れません。
部屋を片す時間ももったいないときは、自習室やカフェ、コワーキングスペースなどを活用しましょう。
育て方⑤他者の頑張りを“自分ごと”として受け取る


自分に似た立場の人が頑張る姿を見て、



一緒に頑張ろう。自分もできる!
と、ただ見習うのではなく感情をリンクさせましょう。
育て方⑥自分の感情にラベルをつけてみる
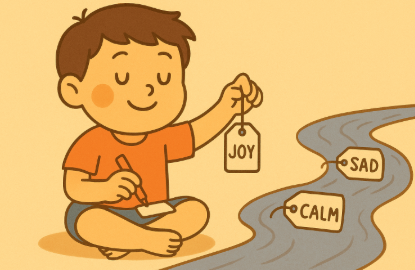
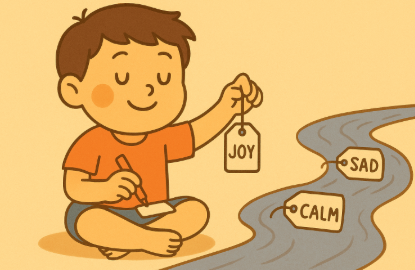
不安や緊張、焦りといった感情に飲み込まれると、
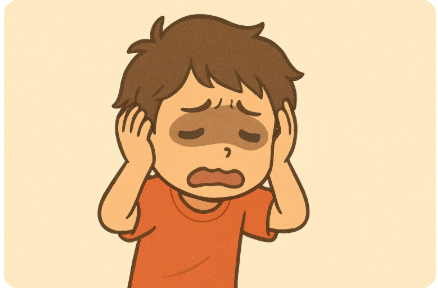
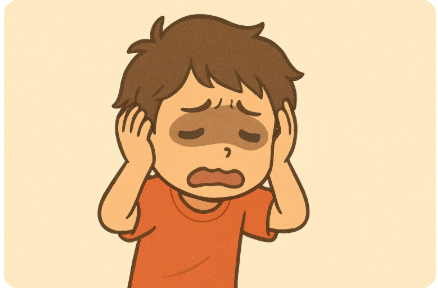
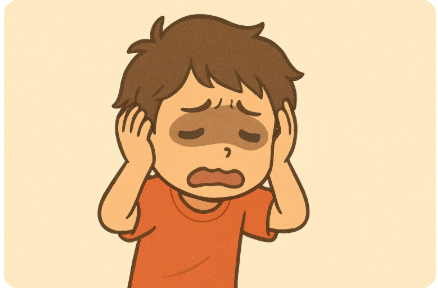
やっぱり無理だ
と感じやすくなります。そんなときは、



今、自分は何を感じているのか?
気持ちを言葉にしてみましょう。



今、不安を感じているけど、それは“初めての挑戦だから”だ!
言語化は、自分を理解するための第一歩です。
自分の心と距離をとれると、落ち着いて「乗り越えられる」と思えるようになります。
仕事と勉強を割り切れないときの「ラベリングの仕方」を確認する(社会人向け記事)
育て方⑦振り返りを習慣化する


週に1度、自分の行動と結果を振り返り、
- 何がうまくいったか
- 何を改善できるか
認識しましょう。
自分を主語にした視点を持つことが、自己効力感を育ててくれます。
なにもできなかったと思う日も、「休息を選ぶ」という必要な行動をしています。
挫折や困難に陥った時の対処法 4選
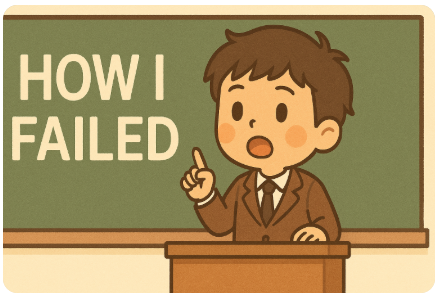
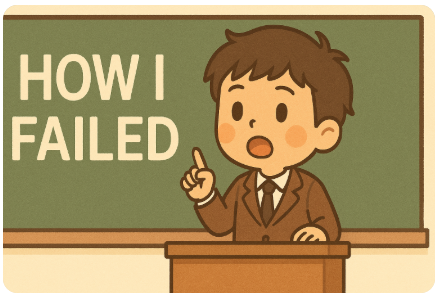
自己効力感を上げようとするとき、挫折や困難にもぶつかります。
困難や挫折をどう乗り越えるかが、長期的な成長のカギに!
困難への対応①視点の転換する


- 失敗を「学習の機会」として視点を転換する。
分析し、改善点を見つけると、失敗も成長の一部となります。 - 「能力は、努力と学習によって向上できる」という認識を持つ。
「もうできない」ではなく「まだできないだけ」です。
困難への対応②周囲の人を巻き込む


家族、友人、予備校などのサポートを積極的に取り入れましょう。
一人で抱え込まないで、頼る勇気も必要です。
困難への対応③セルフコンパッション(自分に思いやりを持つ)


当たり前で難しいことですが、自分を大切にしましょう。
自分を責めるのではなく、優しく励ます声をかけてあげる意識が重要です。
困難への対応④だれかへの貢献
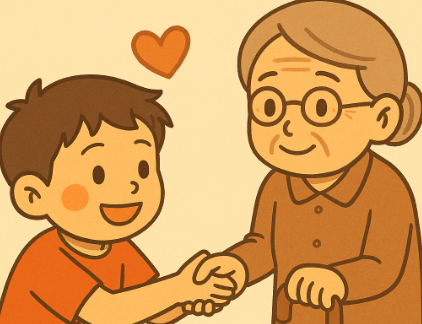
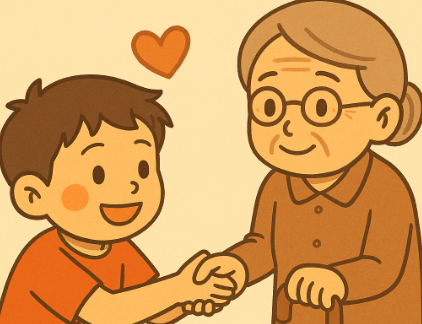
今の時点でもあなたには十分に能力があります。
自分のスキルや経験を誰かに共有すると、自分の能力を再確認できます。
まとめ
- 遂行体験(成功体験)
- 代理的体験(他者の観察)
- 言語的説得(周囲からの励まし)
- 情動的・生理的喚起(気分や体調の影響)
国試における自己効力感の育て方はこちらです。
- 小さな目標を立てる
- 行動のハードルを極限まで下げる
- 成果を可視化する
- 片づいた空間で勉強する
- 他者の頑張りを“自分ごと”として受け取る
- 自分の感情にラベルをつけてみる
- 振り返りを習慣化する
自己効力感を育てる途中、挫折や困難にあたることもあります。
- 視点の転換する
- 周囲の人を巻き込む
- セルフコンパッション(自分に思いやりを持つ)
- だれかへの貢献
急に「自己効力感を高めろ」と言われても難しいですよね。
でも「ちょっとやれてたかも」と気づくことは、誰にでもできる一歩かもしれません。
ハビットトラッカーで小さな積み重ねを可視化すると「ちょっとやれたかも」感が得られる!