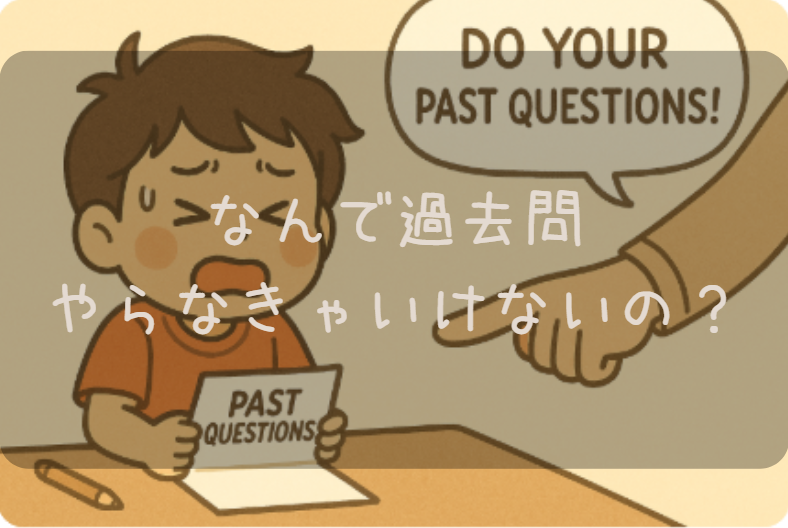この記事では、【問題演習の実験例と効果】がわかります。
「過去問の効果に懐疑的な人」や「勉強方法の判断材料が欲しい人」におすすめ!
- テスト効果は確立された学習効果の一つ
- テストによってアクティブリコールや分散学習、学習の転移が促進される。
- 真剣に問題を解くこと自体が効果を生む。
こんにちは!ゴロ助です。
これって私だけかもしれないのですが、
問題が解けないとき、とりあえず問題を解くことを後回しにしてしまいがちです。
(仲間、、、いませんか?)



解説を読んでも、わけわかめ状態だと効果がなさそうだし、
まずは体系的に学んだ方が、脳に定着しそう。
なにより問題を解けない自分が辛いのなんのって!
それでも、先生は言います。
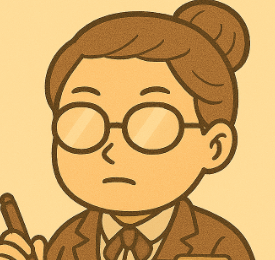
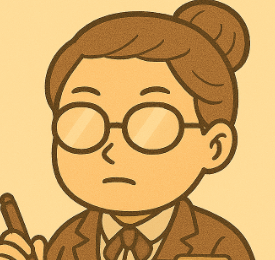
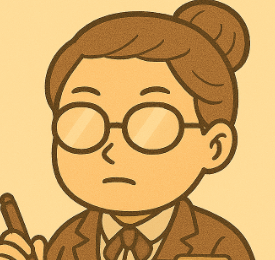
まずは過去問をやりなさい。
- 出題傾向を知れる
- どの部分が問われるかわかる
- 既出問題対策ができる
そういった当たり前のことはさておき、なぜ、そんなに問題演習が効果的なんでしょうか?
一度しっかりと認識してみませんか?
「20%程度は既出問題が活用される可能性がある」とかの基本のキを確認しておく
テストでなにが起きるのか?
記憶・学習メカニズムから見てみましょう。
テスト効果が起きる
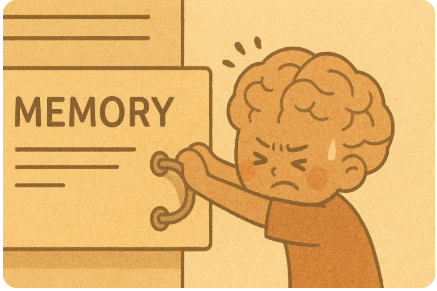
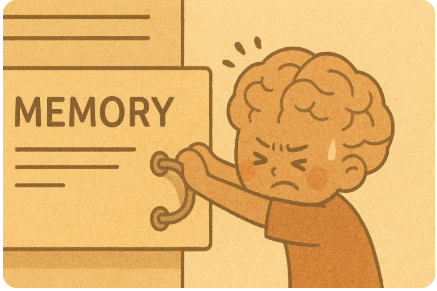
テスト効果は、心理学の研究で確立された学習効果の1つで、
「テストを受けると学習の定着が促進される効果」のことです。
同じ時間で「読み返し」または「テスト」を行う場合、
「テスト」を行った方が記憶定着率が圧倒的に高いことが証明されています。
単語を10回読むより、1回読んで5回テストする方が長期記憶に定着します。
実証実験
3群に分かれて、「60枚の絵を覚える」課題を行い、1週間後に思い出せる枚数を確認する実験を行った。
A群:60枚覚えたら、その場を離れる。
B群:60枚覚えたら、白紙を渡されて、7分間思い出せるだけ思い出すテストを1回すぐに行う。
C群:60枚覚えたら、B軍がやったテストを3回連続で実施する。
・記憶直後のテスト結果(思い出せた枚数)
B群→約32枚
C群→1回目:約32枚、2回目:約35枚、3回目:約36枚
C群は、テストを重ねるごとに成績が向上した。
・1週間後のテスト結果(思い出せた枚数)
白紙に覚えている60枚の絵を記入するテストを実施
A群:17.4枚
B群:23.3枚
C軍:31.8枚
直後にテストを3回行ったC群が1番成績が良かった。
Henry L. Roediger III(2011), Chapter One – Ten Benefits of Testing and Their Applications to Educational,Practice,Psychology of Learning and Motivation,Volume 55, Pages 1-36
つまり、
- テストの回数を重ねると成績が上がる。
- テストをした方が、1週間後も記憶に定着している。
テストをすること自体に意味があるのです。
ただし、テストが難しすぎると、この効果は低下するという意見もありました。
なんでテストは効果があるの?
テストがいいのはわかったけど、なんでなの?
テストは、「アクティブリコール」の1つ
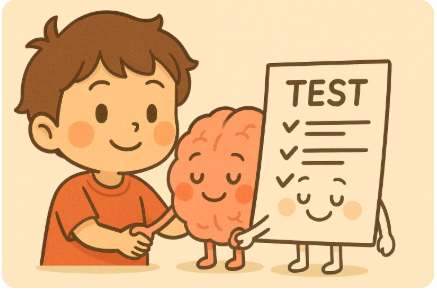
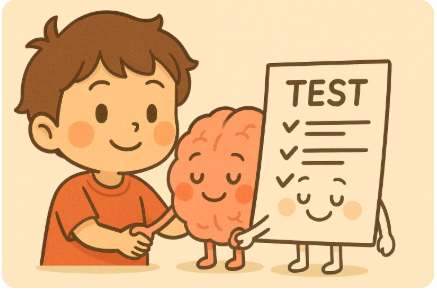
アクティブリコールとは、記憶から情報を能動的に思い出そうとする学習技法・認知プロセスの1つです。
たとえば…
受動的:教科書を読む、講義を聞く
能動的:問題を解く、説明する、思い出す
能動的に学習すると…
- 脳から情報を取り出す練習になる(記憶の検索練習)
- 使った神経回路が強化される(記憶回路の強化)
- 何を知っていて何を知らないかが明確になる
能動的な学習で、単純な暗記ではなく「理解に基づいた記憶」が形成されます。
能動的に情報を取り出せた成功体験は学習意欲を高めることも。
テストによって「分散学習効果」も活用できる
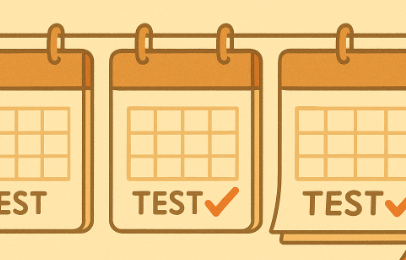
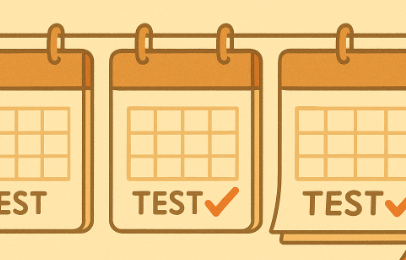
分散学習は、時間間隔をあけて、繰り返し学ぶ方法です。
間隔をあけると、長期記憶として記憶が定着しやすくなります。
過去問などの問題演習を続けると、自然と分散学習に。
テストで「学習の転移」の促進


学習の転移とは、学習した知識をちがう状況に応用する能力です。
たとえば“生物”で学んだ知識を“薬理”で活かすなんてざらにありますよね。
学習の転移を活用することで、学習のコスパが向上します。
過去問を1年分やるだけでも、学習の転移を活用しまくりです。
1教科の青本が終わる気がしないときの突破のカギを確認しておく
テストの効果は挙げきれない!


テストの効果は、多岐にわたります。
- 弱点の発見や対策を考えられる。
- 問題を解く過程で、知識がより深く記憶に刻まれる。
- 異なる文脈を経由して学習すると、記憶の手掛かりが増加し、想起しやすくなる。
・・・・
何よりも、問題形式の慣れと、出題パターンの予測ができます。
そして、出題パターンを知れれば、その後のインプットの作業を大幅に削減可能です。
時間が無い中で、暗記すべきではないポイントを暗記していても仕方ありません。
まとめ:たしかに過去問やらんとね
- 「アクティブリコール」の1つ
- 「分散学習効果」も活用できる
- 「学習の転移」の促進
テストによる効果は相互に作用し合い、学習の好循環を生み出します。
そのため、知識のインプットだけでなく、問題演習によるアウトプット練習が学習において不可欠です!
過去問がなかなか解けないって人はいったん必須問題をやってみるのも手だよ!