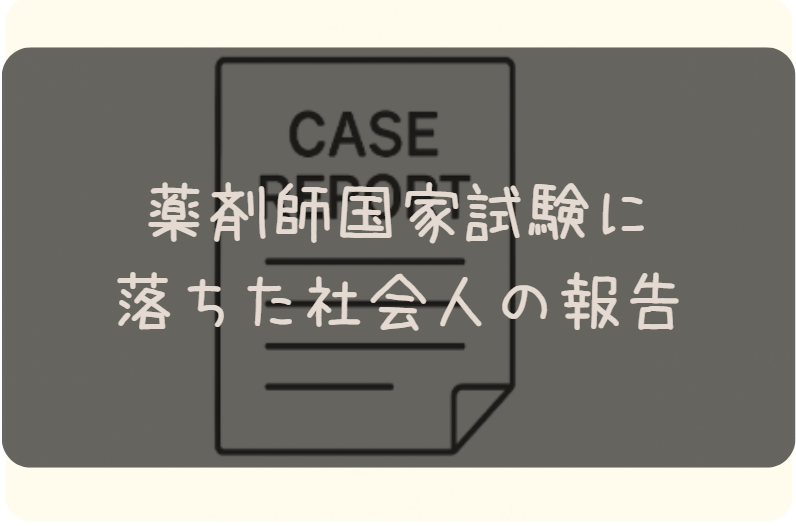この記事では、【実際に落ちた社会人のリアルな状況】がわかります。
「具体的にどんな人が落ちるのか知りたい人」や「これから両立するにあたってどんなことが起こり得るのか知りたい人」におすすめ!
こんにちは!ゴロ助です。
社会人と国試の両立に2度失敗している私の経験から、国試に落ちる社会人の特徴や対策をご紹介してきましたが、
国試に落ちた社会人の具体的な1例報告もしてみたいと思います。
会社によって大きく変わる部分もあると思うので、なんとなくで見ていただけたら嬉しいです。
言い訳しちゃってまったく!くらいの生暖かい目で見てください。
学生との違いはなに?
受験における学生と社会人の一般的な違いはこちらの記事にまとめています。
個人的な違いとしては、初めての土地で一人暮らしを始めたことが大きかったです。
1Kの小さな部屋で、そんなにやることもないのですが、
初めのころは今までに無い緊張感から、平日は家事をする余裕もなく、
家に帰ってお風呂に入って寝るだけの生活でした。
休日は、平日の仕事に備えて、できる限り休息したいという、学生時代には無かった気持ちも強くなりました。
どんな社会人だった?
| 仕事と国試のバランス | 仕事を優先すると決めていた。 |
| 仕事に対する気持ち | 能力が低いことを一生懸命さでカバーしたい |
| 国試に対する気持ち | 合格するまで挑戦すると決めていたが、今年絶対に合格するという覚悟は決めれていなかった。 |
現役で国試不合格だったことによる仕事での影響は?
不合格による影響も職種によってさまざまだと思います。
仕事
免許が必要ない職種だったため、そこまで影響なかったです。
能力至上主義の会社ではなかったことも幸いし、同期と仕事の評定はほぼ変わりませんでした。
ただし、現役で国試不合格ということは、頭が良くはない/効率が悪いという連想はされてしまうと思います。
でも不合格の事実は変えようがないので、評価を補えるように一生懸命働けばよいのだと先輩にアドバイスいただきました。
会社としても、国試に合格する能力のある人材を採用したつもりだったはずなので、
国試に落ちるという能力の低さと向き合いながら、努力しつづける形でした。
実際同じ会社に、国試に落ちてすっぱり諦めて仕事をしている人がいて、その人はおおいに活躍して、評価も高かったです。
対人
同期
後でぬるっと知られるのも気まずいと思い、不合格だったと初めに宣言しておきました。
宣言はしてもしなくても問題はなかったと思います。
優しい同期に恵まれたことで、薬学部出身だと自分が使ってよかった資料を譲ってくれた人もいました。
上司
会社づてで不合格は知られていたので、今後受験をどうするつもりなのか聞かれました。
どんな人が上司になるかによって会社が違うと感じるくらい環境が変わることもあります。
運よく、私の上司は、受験継続に寄り添ってくれる方で、ありがたかったです。
国試受験の宣言をすることは、メリットもデメリットもあります。
やってない時に国試の勉強をしていると言われたり、仕事を普通にしていると仕事のしすぎと怒られたり程度はありましたが、本当によくしていただきました。
関わりの少ない人
雑談で何学部か聞かれることがあり、薬学部と答えると、だいたい8割の確率で、
『じゃあ薬剤師なんだね』と言われます。
その時にどう答えるかは決めておくと慌てずに済みます。
国試に落ちたという事実が、信用に影響してしまうお客さんがいる場合は、
事前に回答を先輩に相談しておくとよいです。
後輩ができてからは、薬学部出身の後輩に不合格を知られるのは、かなり恥ずかしかったです…!
1年目のスケジュールなどはどんな感じ?
前半
前半は研修が多かったので、定時に終わりがちでした。
課題はあるものの、業務の負担は少ないため、1番の受験勉強チャンスだったと振り返ると思います。
仕事での周りとの些細な差が大きな差に感じられて、周りに置いて行かれないようにすることに必死にもなりがち。
後半
後半からは、がっつり業務も始まりましたが、負担は1年目が最も楽でした。
仕事での帰宅が24時近くになることも稀にありましたが、業務外として、朝1時間、夜5時間は時間を確保できました。
ただ、仕事に関して自己学習をする必要があり、国試の勉強だけに費やすのは案外難しかったです。
(自分で割合を決断する必要がある)
年末年始は、業務や忘年会など必須のイベントも忙しいので、コツコツ勉強を進めていくべきと実感しました。
異動があるのか、異動があるならどんなサイクルなのかでも月ごとの忙しさは変わりそうです。
休憩時間について
私の場合ですが、昼休憩はチームで一緒に外食に行って、帰ってきたら業務開始でした。
覚悟が決まってなくて、勉強があるのです…とは言えなかったです。
一緒にご飯に行かない職場もあります!
休日
環境の変化が大きかったので、土日に寝込むときもありました。
時間があっても、やる気が出ませんでした。
なんなら自分に激甘マンがひょっこり顔を出して、とことん休みたかったです…
やる気がでないのはただの“状態異常”?やる気が出ない原因と対策
業務外
飲み会による人との付き合い方も、人によって大きく変わる部分です。
私は、取捨選択ができず、ほとんど参加していました。
小括
一緒に過ごす同期も友人もだれ1人国試の勉強していない環境で、
「現役合格できなかったメンタルよわよわ人間」が、「直近必要ない資格の勉強」を継続するのは至難の業でした。
良い悪いではなく、自分の性質としっかり向き合うべきです。
2年目以降のスケジュールなどはどんな感じ?
2年目以降は、がっつり業務が始まりました。
同期との差がひらき始めるのも2年目からだと思います。
2年目以降に気づきましたが、1年目で気になる差は、ただの誤差です。
有意差はつきません。
仕事の責任も残業もどんと増え、1年目よりも時間の確保が難しかったです。
気持ちの面でも、限られた時間を、「国試」に使いたい気持ちが薄れていきました。
私の場合は、国試合格の最大のチャンスは1年目でした。
使用していた教材は?
- 学生時代の薬ゼミの青本
- 過去問(e-REC)
- 薬ゼミの一問一答(アプリ)
- 学生時代の要点集
- 法規と薬理のみ、青本を買い足していました。
- 隙間時間で勉強するために、持ち運びしやすい教材やアプリが活躍しました。
- 新しい教材をやるというのは、外部の協力がないと難しい気もします。
全部ちょろちょろりしかできていません。
独学の場合は、過去問をひたすらやるのが一番やりやすいかも?
国試への気持ちの変化はどうだった?
最初は、「学生時代に合格が全く見えていなかったわけではないからまあ受かるだろう」という甘い考えもありました。
絶対に受かると“覚悟”ができていなかったのもあり、気持ちはどんどん国試から離れる一方。
社会に出て時間がたてばたつほど、国試は後回しになっていきました。
だけど家族の希望もあり、免許はとらなくてはならない。
家族は、仕事を頑張っても喜んでくれる。
免許をとるぞ!でも仕事も頑張る!!
から、
仕事を頑張りたい!!でも免許も取るから…!
に変わっていき、
仕事…免許…人付き合い…息抜き…
と頑張らないといけないのに、すべてが中途半端でした。
薬剤師国家試験に落ちた後「やってよかったこと」「やらなくて後悔したこと」
言い訳ばーっかりだった気がします。
国試の受験はどうだった?
結局、思うように勉強できないまま当日を迎えて、記念受験といっても過言ではなかったです。
不合格だった原因は?
勉強時間、質、メンタルが確保できませんでした。
具体的な理由はこちらの記事にまとめています。
「絶対に今年受かる」と覚悟も決めておらず、娯楽の時間を設けていたり、自分への甘さも捨てきれていませんでした。
模試も、仕事を理由に自宅受験を選んで、結局後回しにしてしまったり、自分の力を見誤っていることが多かったです。
また、実際の合格体験記を見つけられておらず、どうすればよいかわからないまま進んでいました。
1年目の最初から予備校に入って国試から離れないリズムを作るべきだったと思います。
国試の両立で仕事への影響はあったか?
気持ちに大きな影響がありました。
薬剤師の資格がなくても問題ない仕事だったこともあり、
「国試のために頑張りたい気持ち」が、「仕事を頑張りたい気持ち」の反対側にある気がして、
結局、仕事にも国試にも中途半端な気持ちが続いていたように思います。
その中途半端さは、国試にも仕事にも影響していました。
なぜ国試受験を中断したの?
仕事の責任が大きくなっていくほど、
業務時間は仕事のみに集中して考えているけれど、
無意識下で受験勉強に気を取られている可能性は0ではない。
何かトラブルが起きたときに後悔するのは嫌だ!
と思うようになりました。
当時は、うまく割り切ることができなかったです。
学生時代と比べた学習能力の違い
時がたてばたつほど、大学で勉強した蓄積はかすんでいきます。
予備校にお話を聞きに行った際にいただいた
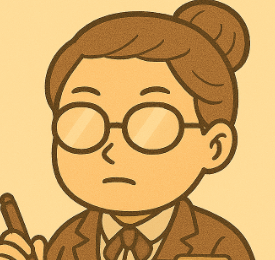
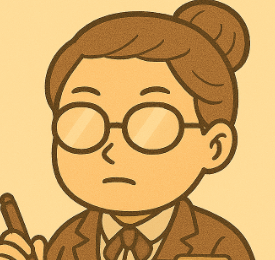
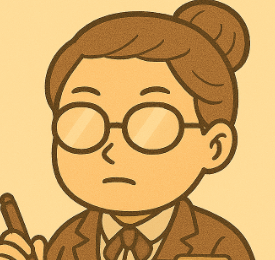
社会人受験は、知識を忘れていることで、新鮮な気持ちで学習できるから脳に刺激が起きて、頭に残りやすいよ!
というアドバイスを胸に学習していました。
今戻れたら合格するためにどうする?
このブログで記事にしていることがすべてですが、
なによりも、
学生・社会人の不合格の特徴の改善する!
特に、
- 1年で絶対に受かると覚悟を決める。
- 1年目の初めに予備校に入る(チューターに監視・指導いただく)。
- 模試を会場で受験する/外に出て模試が終わるまで帰らない。
- 言語化する。
- 予備校の教材をやる時間がなければ、相談の上、要点集周回と過去問演習周回だけど、独自路線に走らない。
(まったく同じスケジュールであれば予備校の教材をやる時間・気力はないので、要点集+過去問になりそうです。)
私の場合は、
自分が持っている限られた時間という財産を、
○○な未来のために、〇対〇の割合で使う。
という意識を固めることも必要だったと思います。
まとめ
社会人での国試挑戦は、今振り返ると、もっとこうしていれば…と感じることも多いです。
結局、転職活動に伴う休職期間の一か月の勉強でギリギリ合格しましたが、
国試を受験すると決めたのなら、かっこよく仕事と両立して、余裕で合格したかった後悔はあります。
仕事がどんなに忙しくても合格できる人もいれば、
私のように勉強できる時間があっても合格できない人もいます。
合格に一番近づけるのは、
「朝早く起きて勉強し、移動時間も休み時間も勉強し、帰ってからも勉強する」
そんな生活パターンだと思います。
でも本当に自分自身の性質や状況として、それが可能なのか。
自分の性質を急に変えることは非常に難しいので、向き合いながら、柔軟に対応していくべきかもしれません。
社会人受験に挑戦する人が、後悔のない挑戦ができることを願っています!