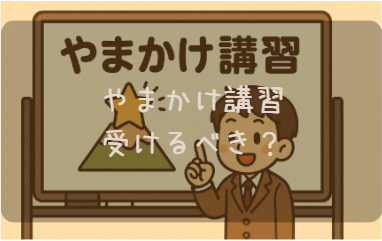この記事では、【やまかけについて・メリット・デメリット・授業を受けるコツ】がわかります。
「やまかけ講習をうけるか迷っている人」や「やまかけ講習の効果を最大化したい人」におすすめ!
こんにちは!ゴロ助です。
私は、全国統一模試Ⅲ 「E判定」(120点以下/345点、下位2%)からギリギリ合格に持ち込みました。
合格に足をかけることができたのは、薬ゼミのやまかけ講習が非常に大きいと感じています。
直前過ぎてやまかけを受講するか迷う人もいると思うので、やまかけをテーマに書きたいと思います。
薬ゼミのやまかけ講習とはなんぞや


大量のデータを持ち合わせた薬ゼミが分析した「今年出るかもしれないヤマ」を授業してくれる講習。
109回までの情報としては、
| 実施タイミング | 国試の2日前あたり |
| 申し込みタイミング | 1月初旬あたり(統一模試Ⅲでもアナウンスがありました) |
| 時間割 | 全教科を半日で実施(1教科10分~20分) |
1教科あたりA4おもてに1枚程度の情報量ですが、かなりの情報量です。
国試直前の直前に実施されます。
やまかけ講座は当たるのか


公式の発表
やまかけ単体ではわからなかったのですが、統一模試とやまかけを合わせてどのくらい当たっているのかを薬ゼミ公式が出しています。
- 108回は131問/345問
- 109回は107問/345問
- 110回は103問/345問
やまかけ単体だともう少し減りそうです。
ゴロ助の実感
私の感覚としては、当たる。



薬ゼミこわ…
と怯えるくらい。
実際に国試当日、
- やまかけで言っていたことが正答の選択肢のとき
- やまかけで教えてもらったから誤答の選択肢が消せるとき
- やまかけで「これこれの周辺もやっておいてください」と言われて、復習したらその辺から出るとき
がありました。
また、教科も該当教科だけで出るわけではなく、教科をまたいで出ていると感じるときもありました。
↓国試の帰り道の感想メモでも怯えていました。
国試当日の実際の記録 編|統一模試Ⅲ E判定からギリギリ逆転合格⑧
なぜ当たるのか
なんでも全国の先生方が力を合わせて作り出してくれているようです。
こんなのを普段の授業でも刷り込んでくれるなら、薬ゼミの授業を受講することって大事だったんだ…と思いました。
薬学部出身の知り合いに、やまかけが当たりすぎて怖かった話をしたら、「国試の出題委員の大学の教授はなんだかんだ無意識に定期試験で出題範囲を出していたりもする。大量の予備校生を抱える薬ゼミはそれらの情報も含めて分析できるんだよ…」という妄想をまことしやかに言っていました…
メリット


メリット①薬ゼミの出題予想を知れる
他の予備校もそうですが、薬ゼミは膨大なデータを持っています。
自分でむやみに勉強するよりも、出題可能性が高い部分を復習可能。
トピックと言われるところは、普通に勉強しているだけではわからないです。
メリット②短時間で全教科の知識の整理ができる
半日で授業してくれるので、そこまで拘束されずに全教科を復習できます。
またオンライン講座もありました。
メリット③少ない資料だからこそ直前に見れる
当たりやすい資料を直前に確認できるって最高じゃないですか?
8枚程度の資料なので、とても薄くて、移動中も確認できます。
デメリット


デメリット①超スピード授業
早口です。え?なんて?という暇はありません。メモをとるのも大慌てです。
デメリット②本番の直前の直前に開催される
本番の2日前は、スケジュールが詰まっている人は、空けるのが苦しいタイミングだと思います。
人によっては、授業中は線を引いたりメモするので精一杯の時間になり、別枠である程度まとまった復習が必須です。
正直大学生のときは、講習当日もついていけないし、復習もできないしで全然活用できませんでした。
デメリット③知識に余裕がある人は、知っている知識であることが多い
基本的な部分も含まれているので、「知っているし」と思う人もいるんじゃないかなと思います。
そういう人にとっては、半日の拘束が長く感じるかもしれません。
でも新規の情報は当たる気がします…
やまかけを最大限活用するための注意点


↓私はこのように活用しました。
実際の授業への取り組み方
片手間にやらない
オンラインで片手間にできる感じのスピードじゃないです。
倍速ですか??ってくらいの先生もいます。
あっというまに過ぎ去るので、全集中で受けるべきです。
また、その日1日の計画は、やまかけにするくらいでもいいくらいです。
10枚弱の資料ですが、やり方によっては意外と時間がかかります。
また、資料にないけど、ここ復習しといてねと指示がある範囲もあります。
ペンを何色も用意しておく。
1つの教科で何色も使うことがあります。
マーカーと色ペンを複数色用意しておくとよいです。
自分なりにラインを引きたい人は上手に使い分けることが必要です。
先生が言うことすべてを書き込む
板書もしてくれるのですが、時間の問題からか、口頭でバーッと言うだけのこともあります。
そして、そこが出ることもあります。
殴り書きでも頑張ってメモしましょう。
汚くなるのが嫌な人は、別の紙にメモしておいて、あとで清書してもよいかもしれません。
復習をする
新しい知識は、1回だけでは覚えられません。
私は、絶対出ると思っていたのに、間違えて覚えていて、大問まるっと不正解になってしまいました。



これ知ってたのに!!!
というのは一番悔しいパターンです。
109回の情報ですが、オンライン受講の場合は、前日に資料がメールされました。
予習もしておくと、「自分が覚えられてない+先生が重要と言っていた」という優先して復習すべきところがわかります。
印刷の必要があるか確認する
109回の時のやまかけオンライン受講では、PDFのダウンロードリンクがメールで送られてきて、講義資料を自分で印刷しました。
どうなるかわかりませんが、印刷環境が無い人は、印刷が必要かどうか注意が必要です。
国試1日目終了後のやまかけ講座的なもの(オンライン)があったら確認する
出題されたところを黒塗りして解説してくれます。
ここでも、先生がぽろっといったところも要注意です
私は、勝手に黒塗りされたところも出る可能性あるだろと思って復習していました。
やまかけが特におすすめな人
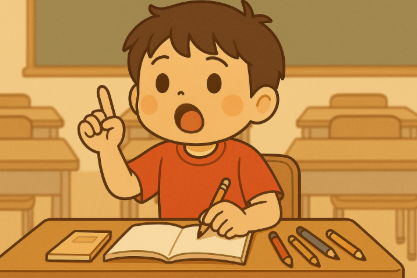
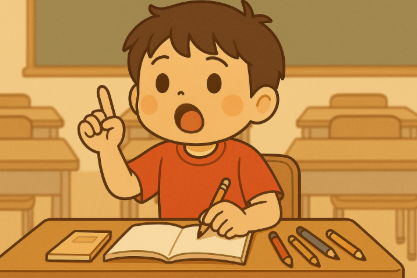
基本的にはおすすめです。
予備校に通っていない人
やっぱり予備校に普段通っていないと、国試に出やすい部分はあまりわかりません。
そんなんどこに載ってん??みたいなところをやまかけで教えてもらったりしました。
全教科を復習したい人
高速で全教科をさらうことができます。覚えているかの確認になります。
直前に見る資料を迷っている人
本番前に見る資料は事前に決めておくべきです。
1時間の密度を最大化するために、“今”すべき準備【試験直前・当日の過ごし方の改善】
模試の時とは違って、休み時間や1日目の夜は、そこまで時間がありません。
直前に見る資料が無い人は、やまかけを確認すると良い気がします。
成績が低い人
私みたいな人は、やまかけで出たとこを覚えているかで合否が変わることがあると思います。
ちなみに、毎年同じなのか
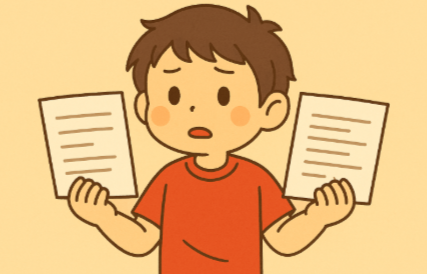
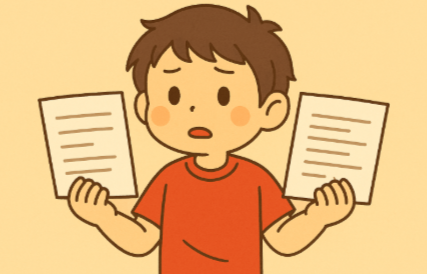
私が大学生の時に受けたやまかけと比較してみましたが、基本的な部分は同じところもありますが、まったく同じではなかったです。
おそらく傾向から基本的な部分も載せるものをその都度分析していそうです。
またその年のトピック的なものは全く違いますし、そこがわりかし出る気がします。
結論
私個人的には、とてもおすすめです。
自分のいままでの勉強も大切にしながら、考えてみてください!